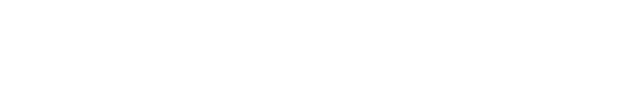女性ホルモンと鼻の症状 ライフステージごとの変化と対処法
はじめに
女性はライフステージに伴うホルモン変動によって、鼻の症状(鼻炎や鼻づまり、鼻の乾燥など)に影響を受けることがあります。たとえば、生理前になると急に鼻が詰まったり、妊娠中に鼻水が増えたりといった経験はありませんか。実は女性ホルモンの変化が鼻の粘膜に作用し、こうした症状を引き起こすことが知られています。
月経周期、妊娠、更年期など各段階で起こりやすい鼻の不調とその原因について解説し、日常でできるセルフケアや受診のタイミングについてもご紹介します。
鼻と女性ホルモンの関係
鼻の粘膜はデリケートで、血管や腺が豊富にあります。この鼻粘膜にエストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンが影響を及ぼすことがわかっています。女性ホルモンの変動によって鼻粘膜の血流や分泌が変化し、鼻づまりや鼻水などの症状が現れることがあります。
例えばエストロゲン(卵胞ホルモン)は血管を収縮させ、プロゲステロン(黄体ホルモン)は血管を拡張させる作用があります。血管拡張は鼻粘膜の腫脹、つまり鼻閉に関連します。そのため、生理周期による鼻詰まりがでる方がいらっしゃいます。このように女性ホルモンのバランス変化と鼻の状態には密接な関係があり、次章以降で詳しく説明する月経周期や妊娠、更年期の鼻症状の背景にもなっています。
なお、女性ホルモンの影響は鼻づまりだけでなく鼻出血にも及ぶことがあります。実際に、生理の時期に鼻粘膜が充血して出血しやすくなる代償月経と呼ばれる現象も報告されています。
これはごく稀なケースですが、ホルモンと鼻粘膜の関係の深さがうかがえます。多くの場合、ホルモン変動に伴う鼻の症状は一時的なものですが、生活に支障をきたすほどつらい場合には適切な対処や受診が必要になります。
月経周期と周期性鼻炎
月経周期とともに繰り返す鼻炎(周期性鼻炎)をご存じでしょうか。生理前後になると毎回のように鼻がムズムズしたり詰まったりする症状は、周期性鼻炎と呼ばれ、ホルモン変動が原因の一つと考えられています。
生理前の黄体期にはプロゲステロンが増加して鼻粘膜の血管が拡張しやすくなるため、鼻粘膜がむくんで鼻づまりが起こりやすくなります。その結果、生理直前から生理中にかけて「風邪でもないのに鼻だけ詰まる」という状態が生じるのです。症状としては鼻づまりが顕著ですが、人によってはくしゃみや鼻水も増えることがあります。特にアレルギー体質の方は、この時期に花粉症やアレルギー性鼻炎の症状が悪化するケースもあります。
医学的にも、生理前の鼻炎症状とホルモンの関係は指摘されており、「月経関連鼻炎」とも呼ばれることがあります。具体的なデータとして、ある研究では月経前に鼻づまりなどの症状が悪化する女性は全体の約20%にのぼるとの報告もあります。
周期性鼻炎自体は生理が始まるとホルモンバランスが変化して徐々に治まることが多いですが、毎月繰り返すつらい症状に悩まされる場合には、低用量ピルの使用などホルモン変動を和らげる治療法が有効なこともあります(※低用量ピルは医師の処方が必要です)。まずはセルフケアとして鼻を温めたり生理食塩水で洗浄したりして様子を見ましょう。
妊娠期の鼻炎
妊娠中も鼻の不調が起きやすい時期です。妊娠をきっかけに発症する鼻炎は「妊娠性鼻炎」と呼ばれ、妊娠16週以降に顕著になることが知られています。
妊娠すると胎児を維持するためにエストロゲンやプロゲステロンが急増し、同時に母体の血液量も増加します。その結果、鼻の粘膜への血流が増えて粘膜が充血し、くしゃみ、鼻水、鼻づまりといった症状が出やすくなるのです。
特に鼻づまりは妊娠中期以降の妊婦さんの約20~30%にみられるともいわれ、妊娠中特有の鼻炎として知られています。加えて、鼻粘膜が柔らかく腫れやすくなるため鼻血が出やすくなったり、頻繁に鼻をかむことで中耳炎になるケースも報告されています。こうした症状は妊娠後期まで続くことがありますが、妊娠性鼻炎は通常、出産後数週間で自然に治るとされています。
妊娠中の鼻炎への対応は慎重さが必要です。妊婦さんは市販の鼻炎薬や点鼻薬の使用に制限があります。妊娠12週未満の初期は薬の使用を控えるケースが多いですが、妊娠中期以降で日常生活に支障が出るほど鼻炎がひどい場合には、胎児への影響が少ないステロイド点鼻薬やケミカルメディエーター遊離抑制薬(アレルギー症状を抑える点鼻薬)などが処方されることもあります。
自宅でできる対策としては、湿度管理(乾燥させない)、ホコリや花粉の除去、そして後述するような鼻の洗浄や蒸しタオルによるケアが有効です。
育児・仕事世代と慢性鼻炎
子育てや働き盛りの30~40代は、生活環境やストレスによって慢性鼻炎に悩まされることが少なくありません。ホルモンという観点では妊娠・出産を経てホルモンバランスが変化する時期でもあり、特に出産直後の授乳期にはエストロゲンが低下しやすく鼻の粘膜が乾燥したり、防御機能が弱まることもあります。
さらに、この世代は仕事や育児による疲労や睡眠不足、ストレスが蓄積しやすい傾向にあります。
こうした要因は自律神経のバランスを乱し、鼻粘膜の血管運動を不安定にしてしまいます。その結果、特定のアレルギーがなくても温度差や強い匂い、タバコの煙などちょっとした刺激で鼻水・鼻づまりが起こる血管運動性鼻炎(いわゆる「非アレルギー性鼻炎」)を発症しやすくなります。例えば朝の通勤で寒い屋外に出た途端にクシャミが止まらなくなるようなケースです。このような症状は「寒暖差アレルギー」と通称されますが、正式にはアレルギーではなく自律神経の乱れによる鼻炎です。
慢性鼻炎は放置すると集中力の低下や睡眠の質の悪化を招き、仕事や育児のパフォーマンスにも影響します。忙しい世代だからこそ、以下の点に気を付けて鼻の健康を守りましょう。
-
生活リズムを整える: 十分な睡眠とバランスの良い食事で体調を整えることは、鼻粘膜の抵抗力維持にも役立ちます。
-
ストレスケア: 適度な運動やリラックス法でストレスを溜めないようにしましょう。ストレスはアレルギー性鼻炎も悪化させると言われています。
-
環境対策: タバコの煙や埃っぽい環境を避け、室内は適度な湿度(50~60%程度)を保つよう心がけます。エアコン使用時は加湿器も併用すると良いでしょう。
-
市販薬の扱い: 市販の点鼻薬(血管収縮薬)は即効性がありますが、長期連用はかえって鼻づまりを悪化させる原因(薬剤性鼻炎)になります。使用は連続1週間程度に留め、それ以上使う場合は耳鼻科で相談してください。
以上のセルフケアを行っても慢性的な鼻炎が続く場合、アレルギー検査や専門的な治療が必要なケースもあります。
更年期のドライノーズと嗅覚の変化
更年期(平均閉経年齢は50歳前後)になると、卵巣機能の低下に伴いエストロゲン分泌が大きく減少します。このホルモン変化により、肌や粘膜が乾燥しやすくなる「ドライシンドローム」という状態が起こります。
鼻も例外ではなく、更年期の女性には鼻の中が乾燥する「ドライノーズ」の症状が増えるといわれています。ドライノーズになると鼻の中がムズムズ・ヒリヒリし、かさぶたができたり、ちょっと触れただけで鼻出血しやすくなったりします。
鼻は外からの細菌やウイルスを防ぐバリアでもありますが、乾燥によってそのバリア機能が低下すると感染症にかかりやすくなる恐れもあります。更年期以降、「最近鼻が乾いて違和感がある」「鼻血が増えた」という場合は、ドライノーズの対策をとることが大切です。
また、更年期は嗅覚(においを感じる能力)の変化も起こりやすい時期です。加齢によって嗅覚受容体の機能が低下することに加え、エストロゲン低下が嗅神経や粘膜に影響を与える可能性があります。そのため「以前より匂いを感じにくくなった」「匂いの感じ方が変わった」と感じる女性もいます。一方で、更年期に入ってから特定の匂いに敏感になる方もおり、ホルモンバランスの変動が自律神経に作用して嗅覚過敏を引き起こすケースも報告されています。
いずれにせよ、更年期の嗅覚変化はゆるやかなものが多いですが、急激な嗅覚低下(嗅覚障害)や異臭症(実際にはない臭いを感じる)は他の疾患の可能性もありますので、その場合は専門医を受診してください。
更年期のドライノーズ対策としては、室内の湿度管理や生理食塩水スプレー等で鼻粘膜を潤すことが有効です。市販の鼻腔保湿剤(ワセリンやグリセリン入りのジェル)を綿棒で鼻の中に塗るのも効果的ですが、塗りすぎて喉に垂れると不快ですので少量に留めましょう。また、必要に応じてホルモン補充療法(HRT)により粘膜症状が改善する場合もあります。鼻だけでなく、目や口の乾燥など更年期に複数の乾燥症状がある場合は、ドライシンドロームとして漢方薬などを含めた治療を検討しても良いでしょう。
アレルギー性鼻炎と日常習慣
アレルギー性鼻炎(花粉症やハウスダストアレルギーなど)は男女問わず非常に一般的な鼻の病気ですが、その症状の出方や感じ方には生活習慣が大きく影響します。
女性の場合、先述したように月経前や妊娠中にアレルギー症状が悪化しやすいことがありますが、日頃のセルフケアでも症状を軽減することができます。アレルギー性鼻炎の三大症状はくしゃみ、鼻水、鼻づまりで、特に季節性の花粉症では毎年多くの方が悩まされています。日本ではスギ花粉症の有病率が年々増加しており、2019年時点で国民の約42.5%が花粉症に罹患していたとのデータもあります。
日常習慣のポイントとしてまず挙げられるのは、アレルゲンの回避です。花粉症であれば、飛散シーズン中は外出時にマスクや眼鏡を着用し、帰宅時には衣服や髪に付着した花粉を払い落としてから室内に入りましょう。室内では空気清浄機を活用し、換気は花粉の少ない時間帯に短時間行うなど工夫します。ダニ・ホコリが原因のハウスダストアレルギーなら、寝具をこまめに洗濯し掃除機をかける、床に絨毯やぬいぐるみを増やしすぎないといった環境整備が効果的です。
次に、鼻のケアも習慣にしましょう。朝晩の鼻うがいは、生理食塩水で鼻腔内のアレルゲンや粘液を洗い流せるのでおすすめです。市販の鼻洗浄キットも使えますし、食塩とぬるま湯で自作することもできます(濃度0.9%の食塩水を人肌程度に温めて使用)。鼻腔を清潔に保つことで、粘膜の炎症を抑え症状を和らげる効果が期待できます。
さらに生活習慣全般では、前章でも述べた十分な睡眠と栄養バランスが基本です。アルコールの摂取は一時的に血管拡張を招き鼻づまりを悪化させることがあるため、鼻炎がひどい時期は控えめにしましょう。また入浴で体を温め寝る前に鼻通りを良くしておく、適度な運動で免疫機能を正常化するといった心がけも大切です。日常習慣の改善だけでは症状がコントロールできない場合は、医療機関でアレルギー薬の使用も検討してください。抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻薬など適切な薬物療法と組み合わせることで、日常生活の質を大きく向上させることが可能です。
香り製品と化学物質過敏症
最近は柔軟剤や香水、消臭剤など様々な香り付き製品が日常生活で使われていますが、人によってはこうした人工的な香りや化学物質に敏感に反応し、鼻や体調に不調をきたすことがあります。周囲には良い匂いでも、自分には鼻がムズムズしたり咳が出たり頭痛がするという場合、それは化学物質過敏症(かがくぶっしつかびんしょう)かもしれません。
化学物質過敏症はある特定の物質だけでなく、香料、塗料、洗剤、防虫剤など日常の様々な化学物質がトリガーとなり得るのが特徴です。症状も鼻炎だけでなく、喉の痛み、咳、めまい、皮膚のかゆみなど多岐にわたります。アレルギー性鼻炎と異なり明確な免疫反応の仕組みは解明されていませんが、微量の化学物質に繰り返し曝露されることで過敏状態に陥ると考えられています。日本では香害(こうがい)という言葉も生まれ、社会問題として認識され始めています。
対策としては、まず原因となる香り製品や化学物質から距離を置くことが基本です。職場や学校など自分で環境を選べない場では、マスクの着用や換気である程度の軽減が期待できます。また周囲の人に理解を求めることも大切です。例えば職場で強い芳香剤が使用されている場合、症状がつらいことを相談すれば配置転換や製品変更など対応してもらえる場合もあります。
副鼻腔炎
副鼻腔炎(ふくびくうえん)は、鼻の周囲にある空洞(副鼻腔)に炎症が起きる状態で、蓄膿症(ちくのうしょう)とも呼ばれます。風邪から細菌感染を起こす急性副鼻腔炎と、炎症が何ヶ月も続く慢性副鼻腔炎に大別されます。症状は鼻づまりや膿性の鼻水、匂いが分かりにくいなどが特徴で、慢性化すると治療に時間がかかります。
日本では慢性副鼻腔炎の新規患者数は年間100~200万人程度(人口の約1%前後)にのぼり、決して珍しくない病気です。基本的には抗生物質の投与やネブライザー治療、必要に応じて内視鏡手術で膿や鼻茸(ポリープ)を取り除くことで多くは改善します。
しかし、中には通常の治療ではなかなか良くならない難治性の副鼻腔炎も存在します。その代表が好酸球性副鼻腔炎です。好酸球とは白血球の一種で、アレルギー反応や寄生虫防御に関与する細胞ですが、この好酸球が副鼻腔の粘膜に大量に集まって炎症を起こすタイプの副鼻腔炎があります。好酸球性副鼻腔炎では両側の鼻腔に多数の鼻茸(ポリープ)ができ、内視鏡手術で取り除いても再発しやすいという特徴があります。ステロイド薬が奏効しやすい一方で、ステロイドを止めるとまた悪化してしまうため治療が難しい病気です。日本でも1990年代後半から報告が増え始め、近年患者数が増加傾向にあります。推定では慢性副鼻腔炎で手術を受ける患者さんのうち50~60%がこの好酸球性副鼻腔炎に該当するとのデータもあり、決して稀な存在ではありません。好酸球性副鼻腔炎は気管支喘息を合併することも多く、特にアスピリン喘息(解熱鎮痛薬によって誘発される喘息)を持つ方は非常に高率に合併します。もし嗅覚の著しい低下や鼻茸による強い鼻づまり、そして喘息の併発がみられる場合、この疾患を疑って専門医の診断を受けることが重要です。
治療はステロイド内服や生物学的製剤(抗IL-5抗体など、難治喘息にも用いられる注射薬)の併用を含め、耳鼻科と呼吸器科が連携して行うケースが多いです。好酸球性副鼻腔炎は国の指定難病にもなっており、治療費助成の対象となる場合もあります。慢性的な鼻づまりや嗅覚障害でお悩みの方で、「ただの蓄膿症にしては治りにくい」という場合は、このような新しい概念の副鼻腔炎が背景にないかどうか、一度専門の医師に相談してみましょう。
自宅でできるセルフケアルーティン
ここまで様々な鼻の不調について述べてきましたが、共通して言えるのは日々のセルフケアが症状緩和に役立つということです。以下に、自宅で簡単にできる鼻ケアのルーティンをまとめます。毎日の習慣に取り入れて、鼻の調子を整えましょう。
鼻うがい(鼻洗浄)
生理食塩水を用いた鼻うがいは、鼻の中に溜まったホコリや花粉、粘液などを洗い流し、鼻通りを良くする効果があります。市販の鼻洗浄器具を使っても良いですし、人肌程度のぬるま湯に食塩を溶かして自作することもできます。ポイントは、食塩水の濃度を0.9%前後(生理食塩水と同じ濃度)にすることと、顔を前傾させて片鼻ずつゆっくり流し込むことです。鼻うがいをすると一時的にスーッと息がしやすくなり、また粘膜表面のアレルゲン除去にも有効なため、アレルギー性鼻炎の予防・軽減にも役立ちます。朝の支度前やお風呂上がりなど、1日1~2回の習慣にしてみましょう。ただし、痛みを感じる場合は食塩水の濃度や温度が適切か確認し、無理のない範囲で行ってください。
蒸しタオルで鼻を温め保湿
鼻づまりの解消には温めたタオルを鼻に当てるケアも効果的です。これはいわゆる「鼻カイロ」とも呼ばれる方法で、濡らしたタオルを電子レンジで温めて鼻の付け根に当て、鼻全体を温めます。蒸気によって鼻粘膜に潤いを与えるとともに、温熱で血行が良くなり鼻腔が広がるため、一時的ではありますが鼻づまりの改善が期待できます。朝起きたときや就寝前、あるいは日中でも鼻が詰まって苦しいときに試してみましょう。加えて部屋の湿度を適度に保つことも大切です。特に冬場は空気が乾燥しがちなので、加湿器を使用したり、濡れタオルを部屋に干すなどして湿度50~60%を目安に調整してください。湿度管理はドライノーズの予防や風邪・インフルエンザ予防にも有効です。
正しい鼻のかみ方
意外と見落としがちなのが鼻のかみ方です。鼻水が出るときに強く何度もかんでいませんか? 実は強すぎる鼻かみは、粘膜を傷つけたり耳に圧力をかけて中耳炎を引き起こすことがあります。鼻をかむときは片方ずつ押さえて、優しくゆっくりとかむようにしましょう。たまった鼻水をこまめに出すこと自体は大事ですが、力任せにかむのではなく、ティッシュで頻繁に拭き取る・すすり上げずに早めにかむといった工夫をしてください。特にお子さんやご高齢の方は耳管(耳と鼻をつなぐ管)が弱いので注意が必要です。
鼻を守る習慣
日々の中で鼻の健康を守るちょっとした習慣も取り入れましょう。外出後の手洗い・うがい・鼻洗いは、花粉やウイルスを体内に持ち込まない基本的な防御策です。就寝時に枕を少し高くする(頭を高めにする)と、鼻づまりで呼吸しづらい場合に楽になります。寝室の空気清浄や就寝前の点鼻薬なども状況に応じて活用しましょう。こうしたセルフケアルーティンを継続することで、「気づいたら今年は鼻の調子がいい」と感じられるようになるかもしれません。
受診の目安
鼻の不調に対してセルフケアを行うことは大切ですが、場合によっては早めに医療機関を受診すべきサインもあります。以下に、専門の受診を検討したほうが良い目安を挙げます。当てはまる症状がある方は、我慢しすぎず耳鼻咽喉科などで相談してください。
-
長引く症状: 鼻づまりや鼻水、くしゃみなどの症状が2週間以上続く場合は、単なる風邪ではなくアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎に移行している可能性があります。特に感冒(かぜ)は通常1週間程度で改善するため、それ以上続くときは受診を検討しましょう。
-
強い痛みや発熱: 顔面の頬や額に痛みを伴う、あるいは38℃以上の発熱がある場合は、副鼻腔炎が悪化している恐れがあります。細菌感染による副鼻腔炎(蓄膿症)では抗生剤治療が必要になるため、早めに受診してください。
-
嗅覚の異常: 匂いが全く分からなくなった(嗅覚消失)、または本来ない臭いが常に感じられる(異臭症)など嗅覚に明らかな異常が出た場合は専門医の診察が必要です。鼻茸の発見や中枢神経の検査など、原因を突き止めるための検査を受けましょう。
-
繰り返す鼻出血: ときおり出る程度の鼻血は心配いりませんが、頻繁に鼻出血を繰り返す場合は粘膜の酷い乾燥や高血圧、腫瘍性病変などが隠れていることもあります。特に更年期以降で粘膜の萎縮が進んでいる方は注意し、必要なら止血処置や薬物治療を受けてください。
-
市販薬で改善しない: 抗ヒスタミン薬や点鼻薬など市販薬を試しても症状が改善しない場合、それ以上自己判断で薬を増やすのは危険です。医師は症状に応じて処方薬や他の治療法を提案できますので、早めに相談しましょう。
-
その他心配な場合: 妊娠中の鼻炎で呼吸が苦しく眠れない、化学物質過敏症が疑われ日常生活に支障が出ている、いびきがひどく睡眠時無呼吸症候群が疑われる等、少しでも不安な点があれば受診して構いません。 早期診断・治療により、つらい症状が軽減できる可能性があります。
鼻のトラブルは放っておくと慢性化しやすく、生活の質を下げてしまいます。一人で悩まず、適切なタイミングで専門家の力を借りてください。鼻の健康を保つことで、毎日の快適さは格段に向上します。辛い鼻の症状に悩む方が、一日も早く笑顔で過ごせるよう願っています。
『池袋ながとも耳鼻咽喉科』の公式ブログです。病気の情報、クリニックの情報発信をしていきます。院長の長友孝文は日本耳鼻咽喉科学会専門医。北池袋駅より徒歩2分、板橋駅より徒歩7分の北池テラス4Fにある耳鼻咽喉科クリニックです。