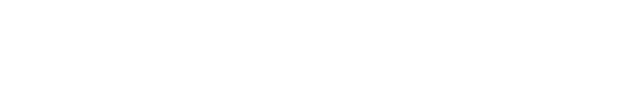頭頸部がんについて
頭頸部がんとは?
首から上に複数の症状がある場合や、症状が漠然として部位を特定できない場合、「のどが痛くて、食べ物が飲み込みにくい。あごの下に違和感がある…」などという症状がある場合、病院に行っても何科を受診すればよいか迷います。
頭頸部を診療範囲とするのは「耳鼻咽喉科」です。耳鼻咽喉科というと、耳、鼻、のどの病気だけを扱うと思っている人も多いようですが、口内炎や舌の痛みなども耳鼻咽喉科が担当します。意外と知られていませんが、耳鼻咽喉科は診療範囲が広いのです。
頭頸部にできた「がん」も、耳鼻咽喉科の領域です。ただ、頭頸部のがんは手術治療が中心となるため、手術に際しては「頭頸部外科」という専門領域があります。
首から上の不調で何科に行けばいいか迷った場合や、症状にがんの疑いがある場合は、まずは耳鼻咽喉科を受診してみてください。
視診
特に口腔内や咽頭内の腫瘍は視診が重要です。表面が不整であること、易出血性(出血しやすい)であること、広基性(キノコのように生えている(有茎性)のでなく、山のすそ野のように広がって存在している)であること、辺縁不明瞭であることはより悪性腫瘍をうたがう所見です。
触診
口腔内の腫瘍、頸部の腫瘍は触診が重要です。腫瘍が硬ければ硬いほど、動きが悪ければ悪いほど悪性腫瘍をうたがいます。痛みを伴うケースは比較的少ないため、痛みの有無のみで判断するのは危険です。
細胞診、組織診(※当院では施行できません)
癌が疑われる病変があった場合は必ず施行される検査です。頭頸部がんの場合は、この検査なしにがんと診断することはないと言っても過言ではありません。病変の一部を取り(穿刺、擦過、切除など様々な方法があります)、顕微鏡レベルで癌細胞の有無を確認する検査です。通常は大きな病院でなければできないため、生検が必要そうな病変を認めた場合は、大学病院にご紹介させていただいております。
血液検査
癌と一口にいっても種類はたくさんあり、それぞれにおいて血液検査で調べる腫瘍マーカーはバラバラです。頭頸部癌や食道癌、肺癌といった名称はあくまで部位を表しており、発生母地の組織によって扁平上皮癌や腺癌、乳頭癌、神経内分泌癌などの種類に分類されます。(「胃に発生した腺癌」といった言い方です。)その種類それぞれに応じた血液検査の数値が、腫瘍マーカーと呼ばれるものです。がん検診では必要に応じて必要な腫瘍マーカーも測定しますが、あくまで補助として用いられるもので、値が高い=癌があるということではありません。頭頸部がんは90%が扁平上皮癌という組織型になるため、そのマーカーとなりうるSCC、CYFRA、CEAを測定します。
内視鏡検査
1960年代に光ファイバーが開発され、内視鏡の歴史が始まりました。1980年代からスコープの先端にCCDカメラを装着できるようになり、2007年1月からオリンパス社からNBI(Narrow Band Imaging)が発売され、ハイビジョン画像と組み合わせることで詳細な観察と癌の早期発見が可能となっています。NBIとは、早期癌の特徴である粘膜直下のらせん状の毛細血管を、限られた波長の光源で観察することで目立ちやすくし、一般的な白色光では見えにくい早期の病変を発見しやすくするものです。癌も早期に発見できれば、内視鏡治療や外来での放射線のみの治療など、比較的負担の少ない治療法が選択できます。
超音波検査(エコー検査)
超音波検査は、産婦人科の検診や肝胆膵の消化器内科などでなじみ深い検査です。簡便で痛みを伴わず、CTなどのような放射線の被ばくの心配もないため、非常に汎用性が高い検査となっており、頭頸部領域においても頻用されます。
甲状腺、耳下腺、顎下腺、頸部リンパ節などにある腫瘍の性状を確認できることはもちろん、腫れている原因が腫瘍なのか、炎症なのか、膿瘍(うみ)を作っているのかなどがある程度類推できます。良性なのか悪性なのか、どのような細胞から腫れものが成り立っているのかを確認するためには、穿刺吸引細胞診が必要です。こちらに関しては、当院では対応できないため、高次医療機関へご紹介して行う検査になります。
CT・MRI(※当院では施行できません)
病変の有無を客観的に評価する検査で、がんの「ステージ」を決定するために必須の検査です。がんを診断した場合は必ず行われます。
一方で、CTやMRIはある程度の病変のサイズがないと同定はできませんので検診としての検査には不向きです。逆に頚部の腫れなどがある場合は有用です。検査装置がないとできませんので、当院では施行できないため、もし必要と思われたら他施設を紹介しております。
PET検査
行える施設に限りはありますが、がんが疑われる場合や治療前に遠隔転移を確認する場合に行うことがあります。
早期発見の重要性
例えば咽頭がんの場合、早期発見、早期治療ができれば、全身麻酔は必要ですが、癌と周辺の粘膜を切除可能で内視鏡を使用し切除できるので入院も1週間程度、機能障害もほぼ残らずに治療が可能です。しかし、進行した場合、手術であれば喉頭を大きく切除しなければならず、声が出ないなどの重篤な後遺障害が残ることもあり、放射線や抗がん剤での治療ではのどを温存可能ですが治療の影響でのどの違和感や、食事ができなくなるなどの症状が出現する可能性があり生活の質が大きく低下します。早期に発見し早期の治療が非常に重要となります。
頭頸部がんには、早期発見のための定期健康診断がほとんどないため(一部の自治体では喉頭がん検診が行われています)、ご自身で気づき、病院を受診するしかありません。
また、病気を発見するためには当然最新の機器も必要ですが、慣れた眼で見ることが重要です。検診に行かれる際には、ある程度頭頸部がん診療の経験がある医師に診てもらうことをお勧めします。
最新の機械があっても正確な診断眼がないと猫に小判です。10年以上大学で培った診断眼で早期の病変の発見に努めてまいりますので、上記症状に思い当たる場合は受診を検討ください。
当院での検査費用
約5,000円(初診、3割負担の方)
*基本的には保険診療で対応しますが、上記のような症状がない(無症状の)方の受診は、検診に該当します。この場合、保険診療の対応はできませんので、実費負担していただきます。
検査結果について
*一般的な内科検診のような検診結果の紙はご用意しておりません。
*血液検査以外は即日ご説明いたします。血液検査は結果が出るまで約1週間程度かかります。
頭頸部がんの治療方法
頭頸部がんの治療法には、以下のようなものがあります。
- 手術:がん細胞を摘出する手術。
- 放射線治療:がん細胞を破壊する放射線を照射する治療。
- 化学療法:がん細胞を破壊する薬剤を投与する治療。
- 免疫療法:がん細胞を攻撃する免疫細胞を活性化させる治療。
これらの治療法は、病気の進行度合いや患者の状態によって選択されます。
頭頸部がんの予防法
頭頸部がんの予防法には、以下のようなものがあります。
- タバコやアルコールの過剰摂取を避ける。
- 口腔内を清潔に保つ
- HPV感染を予防するため、適切な性教育を受ける。
- 適度な運動やバランスの良い食生活を心がける。
これらの予防法を実践することで、頭頸部がんの発生リスクを低減することができます。