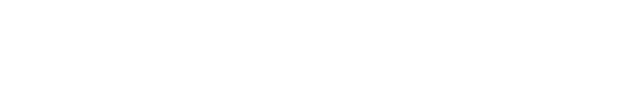マイコプラズマ感染症
マイコプラズマについて
はじめに
マイコプラズマは、特に学童期や若年者に多く見られる感染症の原因となる細菌です。主に呼吸器系に影響を与え、風邪に似た軽い症状から、重篤な肺炎まで幅広い症状を引き起こすことがあります。
この記事では、マイコプラズマの特徴、感染経路、症状、治療法、予防策について詳しく解説します。
マイコプラズマとは?
マイコプラズマは、細胞壁を持たない非常に小さな細菌です。このため、通常の抗生物質であるペニシリン系やセフェム系が効果を発揮しないという特徴があります。マイコプラズマ感染症の中で最も一般的なのが「マイコプラズマ肺炎」であり、これは特に学童期や若年者でよく見られます。
マイコプラズマ肺炎は、全体的には軽症で自然に治癒することが多いですが、場合によっては治療が必要となることがあります。また、無菌性髄膜炎や脳炎などの合併症を引き起こす可能性もあるため、早期の診断と適切な治療が重要です。
感染経路
マイコプラズマの感染は、主に飛沫感染によって広がります。感染者が咳やくしゃみをする際に飛び散る唾液や鼻水に含まれる細菌を吸い込むことで、他の人に感染するのです。家庭内や学校、職場など、人が密集する場所では特に感染リスクが高まります。
潜伏期間と発症
マイコプラズマ感染症の潜伏期間は一般的に2〜3週間程度です(1〜4週間の範囲)。潜伏期間中は自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに感染が広がることがあります。症状が現れると、咳や喉の痛み、発熱、倦怠感など、風邪に似た症状が見られます。
症状
マイコプラズマ肺炎の主な症状には、次のようなものがあります:
- 咳: 初期には乾いた咳が特徴的で、後に湿った咳に変わります。咳が長期間(3〜4週間)続くことがあり、喘鳴を伴う場合もあります。
- 発熱: 軽度から中等度の発熱が一般的です。高熱になることはあまりありませんが、持続的な発熱が続く場合もあります。
- 倦怠感: 体がだるい、疲れやすいといった倦怠感が見られることがあります。
検査と診断
診断が比較的難しく、聴診器で聞いてもほぼわからないこと、迅速検査の感度が高くないことが理由として挙げられます。
- マイコプラズマ抗原検査:もっとも簡便かつ15分程度で結果が出ます。しかし、咽頭から採取するため感染の本体である肺や気管支からは距離が遠く、良好な検体を採取できないことができません。菌が取れなければ、確実な検査にはなりません。検査のタイミング 次第ですが、上気道の菌量は下気道の約1%以下とも言われていますので、咳が出ているときでないと検査をやる意味がありません。
よって、抗原検査は、検出感度が低い(陰性であっても信頼性が低い)のが問題となります。インフルエンザや新型コロナの抗原検査はそれなりに高い感度が報告されていますが、マイコプラズマに関しては50%程度と、とても低いです。検査キット自体は良くなっており、陽性的中率は90%近くなっていますが、検体がしっかりとれないのでは信頼性のある検査になりません。
抗原検査が陰性だからと言って、治療を開始しないと機会損失になりえます。
- LAMP法:マイコプラズマ菌の遺伝子を検出するための迅速で高感度な検査方法です。有用な検査ですが、できる施設は限られており、当院も施行できません。
- 血清抗体検査:患者の血中に存在するマイコプラズマ抗体を測定することで、感染の有無を確認します。初期段階で陽性判定が出ることが少ないため、初期(急性期)・後期(回復期)の2度にわたって採血することが理想的です。
- 胸部レントゲン検査:レントゲンでマイコプラズマの診断は困難ですが、肺炎に至っているかどうかを判断する目的で行われます。※当院では施行できません
治療
- マクロライド系抗生物質:アジスロマイシンやクラリスロマイシンが第一選択となります。これらはマイコプラズマ菌に対して高い効果を示し、比較的副作用が少ないため、特に小児に対してよく使用されます。
クラリスロマイシン 10 日間
アジスロマイシン 3 日間
- テトラサイクリン系抗生物質:ドキシサイクリンなどがマクロライド系に耐性を持つ菌株や、成人患者に対して使用されることがあります。
ミノマイシン 7 日間
ビブラマイシン 7日間
- ニューキノロン系抗生物質:レボフロキサシンやモキシフロキサシンは、重症例や他の抗生物質が無効な場合に使用されます。
レボフロキサシン
トスフロキサシン
適切な抗生物質治療を受けることで、多くの方は症状が軽減し、数日から1週間程度で回復が見込まれます。
※マイコプラズマは自然に回復する感染症で、絶対的に抗生剤が必要な疾患ではないため、あまりあわてて診断したり、抗生剤を使用したりする必要はありません。一般的には、熱や咳がでて2~3日解熱しないときや1週間以上痰の絡んだ咳がつづくときにマイコプラズマを疑い検査や抗生剤を開始します。
予防と感染拡大防止
マイコプラズマ感染症の予防には、日常生活での基本的な感染対策が有効です。以下のような対策を徹底することが推奨されます:
- 手洗い: 外出先から帰宅した際や、食事前などに、石鹸と流水でしっかりと手を洗うことが重要です。
- マスクの着用: 咳やくしゃみが出る場合はマスクを着用し、周囲への感染拡大を防ぎます。また、感染が広がっている時期には、公共の場でのマスク着用が有効です。
- 適切な換気: 室内の空気を定期的に入れ替え、感染のリスクを低減します。
- 十分な休養と栄養: 免疫力を維持するために、バランスの取れた食事と十分な睡眠を心がけましょう。
登園(登校)基準
マイコプラズマは、学校保健安全法で「第三種学校伝染病」にしていされており、急性期は出席停止で全身状態が良ければ登校可能とされておりますが、園や学校に確認されることをおすすめします。