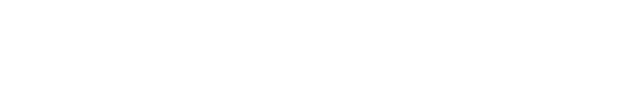突発性難聴
突発性難聴とは何か(定義)
図: 耳の構造。突発性難聴は内耳(蝸牛や内耳神経)の障害による感音難聴であり、音を伝える外耳・中耳には異常がありません。
突発性難聴(とっぱつせいなんちょう)とは、突然発症する原因不明の感音難聴のことです。感音難聴とは、音を感じ取る内耳から脳へ音の信号を送る経路に問題が生じて聞こえが悪くなる状態を指します。典型的には何の前触れもなくある日突然片方の耳が聞こえにくくなることで発症に気づきます。朝起きたときに片耳の難聴に気づくケースもあります。
突発性難聴は左右どちらか一方の耳に起こる場合がほとんどで、両耳同時に発症することは極めてまれです。また、一度発症すると日によって良くなったり悪くなったりといった聴力の変動はみられないのも特徴です。
原因が特定しづらい疾患ですが、早期に適切な治療を開始することで聴力の回復が見込める可能性が高まるため、発症後できるだけ早く治療を始めることが重要です。
突発性難聴の症状
突発性難聴では、以下のような症状が現れます。症状は突然に出現し、主に片耳のみです。症状の程度や組み合わせは人によって様々ですが、多くの場合は発症時に一度きり現れますメニエール病のように何度も繰り返すことはありません)。
片耳の聴力低下(難聴)
数時間から数日以内という短期間で、片方の耳が聞こえにくくなります。軽症では「耳が少しこもる」程度から、重症では会話の声がまったく聞こえないレベルまで様々です。高音域だけ聞こえにくくなるケースでは日常会話の際に気づきにくく、発見が遅れる場合もあります。
耳閉感(じへいかん)
該当する耳に塞がったような圧迫感や詰まった感じを覚えることがあります。
耳鳴り
耳の中で「キーン」という高音や「ゴー」という低音などの持続音が聞こえる症状です。難聴と同時期に耳鳴りが起こることが多いです。
めまい・吐き気
発症前後に激しい回転性めまいや吐き気を伴う場合があります。突発性難聴では基本的にこうしためまいや吐き気の発作は一度きりで、その後繰り返し起こることはありません(反復する場合は他の疾患を疑います)。
※なお、中耳炎のような耳の痛みや発熱は突発性難聴では通常みられません。耳漏(耳だれ)も起こらないため、痛みや耳だれを伴う場合は別の疾患の可能性があります。
突発性難聴の原因(考えられている要因)
突発性難聴の明確な原因は分かっていません(特発性、つまり原因不明の感音難聴です)。発症メカニズムとして有力視されている説はいくつかあります。内耳の蝸牛という器官にある有毛細胞(音を感じ取る細胞)が何らかの原因で障害されることで聴力低下が生じると考えられています。主に以下のような要因が指摘されています:
ウイルス感染説
突発性難聴の直前にウイルス感染症(風邪など)にかかったという報告もあり、ウイルスが内耳に感染して炎症を起こす可能性が考えられています。例えばムンプスウイルス(おたふく風邪)による感音難聴は知られており、突発性難聴もウイルスが引き金となっている可能性があります。
内耳の血流障害説
内耳を栄養する血管の血流が何らかの原因で低下したり詰まったりして、内耳が急性の酸素不足に陥ることで難聴が生じるとする説です。いわば「耳の中で起きる小さな梗塞(耳の中の血行障害)」のようなイメージで、突発性難聴は「耳の卒中」と呼ばれることもあります。ストレスや睡眠不足が続いたときに発症しやすい傾向も指摘されており、これらが自律神経や循環系に影響して内耳の血流不足を招く可能性があります。
自己免疫反応説
体の免疫システムが誤って自分の内耳を攻撃してしまい、有毛細胞がダメージを受ける可能性も考えられています。自己免疫疾患のある方に突発性難聴が起こりやすいとの報告もありますが、明確な因果関係は確立していません。
この他、遺伝要因やストレス・過労、生活習慣病(糖尿病や高血圧など)の関与も指摘されています。実際、ストレスや睡眠不足、糖尿病などの基礎疾患があると発症しやすいともいわれます。ただし、個々のケースで明らかな原因を突き止めることは難しく、ほとんどの突発性難聴は上記のような要因が複合的に絡んだ「原因不明」という扱いになります。
診断のための検査内容
突発性難聴が疑われる場合、耳鼻咽喉科では以下のような検査を行います。診断において重要なポイントは、他の原因で起こる難聴との鑑別(除外)です。特にメニエール病(繰り返すめまいと難聴)、聴神経腫瘍(徐々に進行する難聴だが一部は突発発症する)などは症状が似ているため注意深く区別する必要があります。そのため必要に応じて追加検査も行い、総合的に診断します。
問診(カウンセリング)
発症時期や状況、症状の経過について詳しく尋ねます。併せて既往歴(糖尿病・高血圧・自己免疫疾患の有無など)や服薬中の薬(難聴を起こしうる薬剤の使用歴)、直前の出来事(頭部外傷や飛行機搭乗、過度なストレス等)、家族歴なども確認します。これにより中耳炎など他の疾患や、突発性難聴と症状が似ている病気の可能性を評価します。
耳の診察(耳鏡検査)
耳鏡という器具で外耳道や鼓膜の状態を観察します。耳垢詰まりや中耳炎など外耳・中耳の異常がないことを確認し、難聴の原因が内耳によるものである(感音難聴である)ことを裏付けます。
聴力検査(純音聴力検査など)
防音室でヘッドホンを装着し、さまざまな周波数の音をどの程度聞き取れるか検査します。これにより難聴の程度(軽度~重度)や型(感音難聴か伝音難聴か)が判明します。突発性難聴では通常、片耳の感音難聴(内耳の障害)が認められます。あわせて語音明瞭度(言葉の聞き取り能力)の検査を行うこともあります。
平衡機能検査(めまいの検査)
回転性めまいの症状がある場合は、眼振検査(ゴーグルなどを用いて眼球の動きを調べる検査)や平衡機能検査を行います。これにより内耳の前庭(バランス感覚を司る部分)の状態を評価し、必要に応じてめまいの治療方針に役立てます。
MRI検査 – 聴力検査の結果や症状によっては、内耳から脳までの構造を調べるMRI検査を行います。特に聴神経腫瘍(前庭神経鞘腫)という良性腫瘍が内耳神経にできていると突発性難聴に似た症状を呈することがあり、MRIにて腫瘍の有無を確認します。MRIはトンネル型の装置に横になって入る検査で、痛みはありませんが約30分程度かかります。
以上のような検査結果と総合的な判断によって「突発性難聴」と診断されます。診断確定には他の疾患の可能性を除外することが重要であり、そのため治療と並行して必要な検査を進めることになります。診断後はただちに治療方針を立て、聴力の回復に向けた処置を開始します。
突発性難聴の治療方法(内服、点滴、高圧酸素療法など)
突発性難聴の治療は主に薬物療法を中心に行われます。 発症からの時間経過や難聴の重症度に応じて、入院による集中治療を行う場合と外来(通院)で治療する場合があります(詳細は後述)。一般的な治療内容は次のとおりです。
ステロイド薬による治療(内服・点滴)
突発性難聴の第一選択治療は副腎皮質ステロイドという抗炎症作用をもつ薬の投与です。ステロイドには内耳の炎症や浮腫(むくみ)を抑え、有毛細胞を保護する効果が期待されます。通常はプレドニゾロンなどのステロイド薬を高用量から開始して徐々に減量する方法(漸減療法)で、1~2週間かけて服用または点滴を行います。軽症例では錠剤の内服で開始し、重症例では入院のうえ点滴注射で高容量ステロイドを投与します。ステロイド治療によって一定の割合で聴力の改善が見込めますが、効き目には個人差があります。なお、副作用防止のため胃薬の併用や血糖値のモニタリングを行いながら安全に投与します(副作用については後述)。
高圧酸素療法
必要に応じて高圧酸素療法(HBOT)を併用することがあります。高圧酸素療法とは、専門の高気圧装置の中で高濃度の酸素を吸入する治療です。高圧環境下で血液中に通常の数倍もの酸素を溶け込ませることで、内耳の酸素不足を改善しようとするものです。突発性難聴では発症から2週間以内に行えば聴力回復を助ける可能性があると報告されています。実際の治療では1日1~2回のペースで数日~2週間程度連日実施します。高圧酸素療法は特に重度の難聴例や、ステロイド治療で効果不十分な場合の追加療法(サルベージ療法)として行われることが多いです。治療には専門設備が必要ですが、大きな副作用は少なく安全に受けられる治療です(※閉所恐怖症の方は事前にご相談ください)。
その他の薬物療法の併用
突発性難聴の治療では、ステロイド以外にも内耳の血流や代謝を促進する薬剤(循環改善薬・代謝改善薬)やビタミン剤を併用することが多いです。例えばアデノシン三リン酸(ATP)製剤やビタミンB12製剤、イソソルビド(浸透圧利尿薬)などが補助的に用いられます。これらの薬剤は突発性難聴に対する明確なエビデンスが十分でないものの、内耳の循環や細胞代謝を改善する作用が期待され、現場で広く使われています。医師の判断で副作用や持病との兼ね合いを考慮しながら処方されます。
特にステロイドの鼓室内注入療法はステロイドの全身投与に匹敵する効果が期待できると言われています。糖尿病患者や妊婦などステロイド全身投与による副作用の不利益が大きいケースでは、初期治療から全身投与ではなく鼓室内投与を行うことが推奨されます。しかし、合併症として注射時に一過性のめまいや疼痛が出現することがあったり、鼓膜に永久的に穴が残ってしまうリスクが1~10%あるので注意が必要です。
安静・生活上の注意
薬物治療と並行して、生活環境を整えることも重要です。具体的には、治療中はできるだけ安静に過ごし、静かな環境で心身ともにゆっくり休養するようにします。睡眠不足や過労は内耳の回復を妨げる可能性があるため避けましょう。入院治療の場合は安静臥床が指示されることがあります。自宅療養の場合も激しい運動や長風呂、飲酒など体に負担となる行為は控え、規則正しい生活を心がけます。大きな音に長時間さらされることは聴力に負担となるため、騒音環境もできるだけ避けてください。
上記の治療によって多くのケースで何らかの聴力改善が得られますが、それでも治療開始が遅れた場合や重症例では改善が得られないこともあります。初期治療(ステロイド+必要に応じ高圧酸素など)で効果が不十分な場合、追加の治療を検討することもあります。追加治療としては、鼓室内注入療法(局所麻酔下で鼓膜越しにステロイド薬を中耳に注入し内耳へ浸透させる治療)や、ステロイド以外の薬剤の点滴追加投与などが行われることがあります。最初の治療から2~4週間経過しても回復が不十分なケースで検討される救済措置です。
いつ受診すべきか、早期治療の重要性
突発性難聴は耳鼻咽喉科における緊急疾患の一つです。 聴力の回復には時間との勝負の側面があり、症状に気付いたらできるだけ早く専門医を受診することが望まれます。治療開始が早いほど聴力が改善する可能性が高く、反対に治療の遅れは予後不良の大きな要因となります。具体的には、発症後できれば48時間以内の治療開始が理想的で、この場合約50%の患者で聴力が回復し、改善例を含めると約2/3が良好な経過を辿ったとの報告があります。発症から1週間以内でもできるだけ早く治療を始めれば改善が得られやすいとされています。しかし発症から1か月以上放置すると内耳の障害が固定化してしまい、その後に治療を行っても聴力の回復が得られない可能性が高くなります。
したがって、「おかしい」と思ったら迷わず早めに耳鼻咽喉科を受診することが重要です。具体的には「片耳が急に聞こえづらくなった」「耳が詰まった感じが続く」「突然激しい耳鳴りが始まった」といった症状に気付いた場合、できればその日中~翌日中には受診してください。特にめまいを伴う場合や、補聴器をつけても聞こえないレベルの高度難聴を自覚する場合は一刻も早く受診しましょう。早期に治療を開始できれば、発症から1~2週間以内の治療開始で約60%の患者に聴力の改善が得られるとのデータもあります(完治が1/3、改善が1/3)。大事なのは、「放っておけば治るかも」と様子見をしないことです。突発性難聴は自然回復するケースもあるものの、治療の遅れは取り返しがつかなくなるリスクを伴うため、早期治療で後悔しないようにしましょう。
治療期間と通院の目安
突発性難聴の治療に要する期間は、症状の重さや治療内容によって異なります。一般的な治療期間の目安は約1~2週間です。軽症例で外来治療の場合は、ステロイド内服を10~14日間ほど続けて終了するケースが多くなります。その間は数日おきに聴力の経過を確認するため通院し、症状や副作用のチェックを行います。治療終了時(2週間前後)に再度聴力検査を実施し、回復度合いを評価します。
一方、重度難聴(目安として平均聴力レベルが60dB以上の高度難聴~失聴)や激しいめまいを伴う場合は、入院による集中治療が推奨されます。入院期間はおおよそ7~10日間が目安で、その間にステロイドの点滴治療や必要に応じた高圧酸素療法などを集中的に行います。点滴では「ソル・コーテフ」等のステロイド薬を初日に大量投与し、日ごとに減量していく方法がとられます。入院中は基本的に安静臥床となり、毎日または隔日に聴力検査を行って聴力の推移を観察します。入院加療によって退院時に聴力が十分改善すれば外来フォローに移行し、改善が不十分であれば引き続き外来で追加治療を検討します。
治療期間中は医師の指示通りに薬を服用・点滴し、生活上の注意を守ることが大切です。自己判断で薬の途中中断をしたり無理をしたりすると、せっかくの治療効果が十分得られない恐れがあります。治療終了後も聴力が安定するまで定期的に通院し、経過観察を続けます。多くの場合、発症後1か月程度で聴力の改善具合が最終的に判定できるため、1か月後に改めて聴力検査を行い今後の方針を決定します。残念ながら聴力の回復が得られなかった場合には、補聴器の検討やリハビリテーションについて相談していくことになります(詳しくは「よくある質問」Q6を参照)。
予後と再発リスク
突発性難聴の予後(治療後の経過)は症例によってさまざまです。適切に治療を行っても、完治するのは全体の約1/3程度にとどまります。残りの約1/3は何らかの改善は得られるものの聴力が完全には戻らず、さらに約1/3は残念ながら治療の効果が得られず聴力改善が見られないとされています。もちろん、治療を行わず放置した場合は改善が得られないリスクが一層高くなると考えられます。予後を左右する要因として、発症から治療開始までの時間、高度難聴かどうか、めまいの有無、基礎疾患(糖尿病・高血圧など)の有無、発症年齢(高齢か否か)などが挙げられます。一般的に発症時の難聴が重いほど、また治療開始が遅いほど予後は不良です。逆に軽症で早期治療ができた場合は良好な回復を得やすくなります。
聴力が回復しなかった場合でも、生活上の工夫や補聴器の使用によって不便さを軽減することは可能です。片耳が聞こえにくい場合、周囲の人にその耳側に立たないでもらう、騒がしい環境を避けるといった配慮で会話しやすくできます。また必要に応じて補聴器の装用を検討します。片耳難聴の方向感覚の問題にはクロス補聴器という特殊な補聴器で対応できる場合もあります。高度難聴で補聴器の効果が不十分な場合、人工内耳など外科的治療の適応を検討することもあります。これらについては担当医とよく相談し、自分に合った方法を選んでいきましょう。
再発リスクについてですが、突発性難聴は基本的に一度きりで再発しない場合が多いです。左右のどちらか片耳だけが発症し、その後は起こらないケースが大半を占めます。ただし稀には再発(複数回発症)する例も報告されています。文献によれば突発性難聴の再発率は約0.8%~8%程度とされ、決して高くはありませんがゼロではないようです。再発までの期間は初回発症から平均2年程度であることが多いとの報告もあります。また、反復する難聴発作の背景にメニエール病など他の疾患が潜んでいる場合もあります。再発を防ぐ確実な方法はありませんが、内耳の血流悪化や障害を招きうる生活習慣(過労や睡眠不足、ストレス、高血圧・糖尿病の放置など)を改善することはリスク低減に役立つ可能性があります。一度突発性難聴を発症した方は、今後もう片方の耳も含めて聴力の変化に注意し、少しでもおかしいと感じたら早めに耳鼻科を受診する習慣を持つと安心です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 突然聞こえなくなったのですが、自然に治ることもありますか?
A1. 軽度の突発性難聴であれば自然回復するケースも皆無ではありません。実際、発症から2週間程度の間に徐々に聴力が戻ったという例も報告されています。ただし自然に治る保証はなく、放置することは非常に危険です。治療開始が遅れると聴力が元に戻らない可能性が高まるため、「そのうち治るだろう」と様子を見るのは避けてください。特に会話に支障が出るレベルの難聴が急に起きた場合は、自然回復に期待せずできるだけ早く医療機関を受診することを強くお勧めします。
Q2. 突発性難聴になると入院しないといけませんか?
A2. 必ずしも入院が必要というわけではありません。 突発性難聴の治療は患者さんの難聴の程度や全身状態によって外来でも可能です。軽症で日常会話に支障がないレベルの場合や、事情により入院が難しい場合にはステロイドの内服治療を中心に通院で治療することができます。一方、聴力レベルが60dBを超えるような高度難聴や激しいめまいを伴うケースでは、1~2週間の入院治療が推奨されます。入院することで毎日の点滴治療や経過観察を集中的に行えるメリットがあります。主治医が聴力検査の結果などを踏まえて入院の必要性を判断しますので、指示に従って治療を受けてください。
Q3. 突発性難聴の治療に副作用はありますか?
A3. 主な治療薬であるステロイド薬は短期間の使用であれば安全性は比較的高いです。とはいえ一時的な副作用が現れることがあります。代表的なものは血糖値の上昇、胃の不快感・胃潰瘍、不眠(眠れなくなる)です。そのため治療中は胃粘膜保護の薬を併用し、糖尿病のある方には血糖管理に注意して投与します。他にも一時的な顔のほてりやニキビが出ることがありますが、通常は治療終了とともに消失します。高圧酸素療法には大きな副作用はほとんどありませんが、治療中に耳管が詰まる感じ(軽い耳痛)が出ることがあります(これは減圧時に改善します)。いずれにしても、医師が副作用を抑える対策を講じながら治療を行いますので過度に心配する必要はありません。
Q4. また突発性難聴が再発することはありますか?
A4. 突発性難聴が何度も起こるケースは多くありません。 大多数の方は一度発症すれば、その後は再発しません。ただしゼロではなく、少数例ですが再発が報告されています。研究では再発率は数%程度とされます。再発する場合、初回とは反対側の耳に起こることもあれば、同じ耳に起こることもあります。もし再度「おかしい」と感じることがあれば迷わず受診してください。まれに、繰り返す難聴発作の背景にメニエール病など別の疾患が隠れていることもあるため、再発時には詳しい検査が行われます。
Q5. 突発性難聴にならないように予防する方法はありますか?
A5. 突発性難聴は原因不明疾患のため、「これをすれば予防できる」という確実な方法はありません。しかし、リスクを下げるために日頃からできる対策はあります。まず、睡眠不足や過労を避け、ストレスを溜めないよう心がけてください。過度な飲酒や喫煙も内耳の血流に影響する可能性があるため控えめにしましょう。また生活習慣病の管理も大切です。糖尿病や高血圧がある方は適切な治療でコントロールすることで血管障害のリスクを減らせます。耳のケアとしては、常識的な範囲で大きすぎる音を長時間聞かない(イヤホンの音量に注意する、騒音作業では防音保護具を使う等)ことが挙げられます。なお、通常の耳掃除や適度な音楽鑑賞まで神経質に制限する必要はありませんが、耳に負担となる習慣を避けることが予防の一助になるでしょう。万全な予防法はなくとも、規則正しい生活と耳を大切にする心構えが結果的に突発性難聴の予防につながる可能性があります。万一症状が現れた際にも早期発見・治療につながるよう、耳の異変を感じたら放置しないことが重要です。
Q6. 治療しても聴力が戻らなかった場合、どうすればいいでしょうか?
A6. 残念ながら治療の効果なく聴力障害が残ってしまった場合でも、生活の質を向上させる手段があります。まず、難聴が残った耳については補聴器の使用を検討します。補聴器により残存聴力を最大限活用することで、日常会話の聞き取りが改善する可能性があります。片耳がほとんど聞こえない場合には、健聴側の耳に音を送るクロス補聴器という特殊な補聴システムが有効なこともあります。重度難聴で補聴器をもってしても聞き取りが困難なケースでは、人工内耳という先進的な治療も選択肢となりえます。これらの対応策は耳鼻咽喉科医と相談し、聴力の状態や生活ニーズに応じて検討しましょう。また、聞こえにくい場合は周囲の人にその旨を伝え、話しかけるときは健聴側の耳側から声をかけてもらうなど、生活環境の工夫も大切です。片耳難聴になると耳鳴りが残ることもありますが、音響療法やカウンセリングで適応を助ける方法があります。聴力が戻らなかった場合でも落胆せず、補聴器やリハビリを活用して日常生活を快適に送る工夫をしていきましょう。
最後に強調したいのは、突発性難聴は早期発見・早期治療が何より重要だという点です。一人でも多くの方が適切な時期に治療を受け、聴力の回復につながることを願っています。当クリニックでも突発性難聴が疑われる患者さんには迅速に必要な検査と治療を行っておりますので、「もしかして?」と思ったら遠慮なくご相談ください。聴こえは私たちの大切な感覚です。少しでも異常を感じたら早めに受診し、大切な聴力を守りましょう。