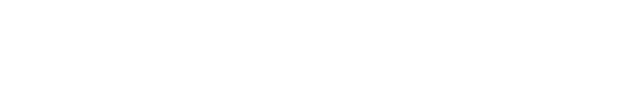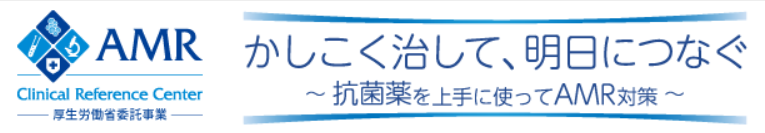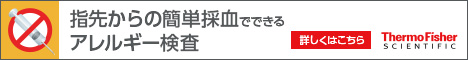小児の耳鼻咽喉科疾患について
小児の『みみ・はな・のど』の特徴
お子さまの耳・鼻・喉(のど)は、大人と比べて構造や機能が未発達なため、風邪などの感染症にかかりやすく、それに伴って様々な症状が出やすい特徴があります。
まず耳についてですが、耳と鼻をつなぐ「耳管(じかん)」が小児では短く、傾きも水平に近いため、鼻の細菌やウイルスが中耳に届きやすく、中耳炎を起こしやすい状態です。特に乳幼児期には風邪のたびに中耳炎になることもありますが、6歳前後から耳管の機能が発達してくると、次第にかかりにくくなっていきます。
鼻の構造にも小児ならではの特徴があります。鼻腔が狭く、上手に鼻をかむことができないため、鼻水が溜まりやすく、長引きやすい傾向があります。また、鼻の奥には「アデノイド(咽頭扁桃)」と呼ばれるリンパ組織があり、成長とともに一時的に大きくなることがあります。アデノイドが肥大すると、鼻づまりやいびき、口呼吸の原因になることがあり、睡眠の質にも影響を及ぼします。ほとんどの場合は成長により自然に小さくなりますが、症状が強い場合は専門的な診察が必要です。
喉にある「扁桃(扁桃腺)」も、免疫を担う重要な器官ですが、幼少期には大きくなる傾向があります。扁桃が大きいお子さまは、いびきや睡眠中の無呼吸を起こすことがあり、必要に応じて治療が検討されます。また、小児は免疫機能がまだ未熟なため、風邪をひきやすく、喉の炎症(咽頭炎や扁桃炎)を繰り返すことも珍しくありません。ほとんどは軽症で自然に治りますが、細菌感染の場合は抗生剤などの治療が必要となることもあります。
このように、小児の「みみ・はな・のど」は発達段階ならではの特性があり、それに伴う症状も多様です。多くは成長とともに自然に改善していくものですが、気になる症状がある場合は、耳鼻咽喉科での早めの診察をおすすめします。当院では、お子さまの年齢や発達に応じた丁寧な診療を行っています。お気軽にご相談ください。
みみの疾患
中耳炎(急性中耳炎)
中耳炎は小さなお子さまに非常によくみられる病気で、特に風邪をひいた後などに耳の痛みや発熱を引き起こします。乳幼児の場合、自分で痛みをうまく訴えられず、頻繁に耳に触れる・機嫌が悪い・夜泣きをする、といった様子で気づくことがあります。耳から液体(耳だれ)が出る場合は鼓膜が破れて膿が出ている可能性があり、早めの受診が必要です。
原因・症状: 中耳炎は鼓膜の奥の中耳という空間に細菌やウイルスが感染して炎症を起こす病気です。小児は耳と鼻をつなぐ耳管が太く短く、ほぼ水平に近いため、鼻や喉の菌が中耳に達しやすくなっています。その結果、風邪に伴って中耳炎を発症しやすく、特に1~3歳頃の乳幼児では繰り返し起こすことも珍しくありません。主な症状は耳の激しい痛みと発熱で、痛みのため夜間に眠れなくなることもあります。痛みでミルクや食事がとれない場合や、高熱が続く場合には注意が必要です。
治療法: 急性中耳炎の治療では、まず痛みを和らげる治療を行います。ご自宅では耳を冷やすと痛みが軽減することがあります。アセトアミノフェンなどの鎮痛薬を使用します。
細菌が原因と判断される場合は抗生物質の内服を数日~1週間程度行います。当院では、お子さまの年齢や症状の重さに合わせて抗生剤を慎重に選択し、必要最低限の期間でしっかり治す方針です。
また、鼻水が多い場合は耳と鼻は繋がっているため、鼻汁の吸引や鼻炎の治療もあわせて行い、中耳炎の早期改善と再発予防に努めます。鼓膜に膿が溜まって鼓膜がパンパンに膨れているような重症例では、鼓膜を小さく切開して膿を出す処置(鼓膜切開)を行うこともあります。処置の際はお子さまが極力怖がらないようしっかり声かけを行い、必要に応じて保護者の方にもご協力いただき安全に進めます。
滲出性中耳炎(耳に水がたまる)
呼びかけても反応が遅かったり、テレビの音量を大きくしがちだったりするお子さまはいませんか?それは滲出性中耳炎による聞こえづらさが原因かもしれません。聞こえの心配で来院されるお子さの多くで、滲出性中耳炎が見られます。
原因・症状: 滲出性中耳炎とは、鼓膜の奥の中耳に液体(滲出液)が溜まってしまう状態です。急性中耳炎のような明らかな痛みや発熱がないため見逃されやすいのですが、難聴(聞こえにくさ)の原因として小児で最も多い疾患です。風邪を繰り返すうちに中耳に粘液が残ってしまったり、アレルギー性鼻炎やアデノイド肥大によって耳管の通気が悪くなったりすることで発症します。
主な症状は軽度から中等度の難聴で、呼びかけに気づきにくい、何度も聞き返す、声がこもって聞こえる、といった形で現れます。小さなお子さんでは周囲が気づきにくいため、保育園・幼稚園の健診や小学校の聴力検査で指摘されて発覚するケースもあります。長期間放置すると聞こえの悪さから言葉の発達が遅れる可能性もあるため注意が必要です。
治療法: 滲出性中耳炎の治療は段階的に行います。まず鼻水や鼻炎の治療、アレルギー対策など原因の改善を図ります。同時に、軽度の難聴で日常生活に大きな支障がなければ経過観察を行い、自然治癒を待つこともあります。
耳管の機能改善のために反復嚥下訓練(つばを飲み込む運動)や風船を鼻に当てて膨らませる耳管通気の訓練(オトベント®)を遊び感覚で行うこともあります。
鼻炎が強い場合は抗生剤や抗アレルギー薬の内服、点鼻薬を組み合わせ、中耳に溜まった液体が吸収されるのを促します。
それでも滲出液が引かず聞こえにくさが続く場合、鼓膜に小さなチューブを挿入して換気を良くする鼓膜チューブ留置術が有効です。この手術により中耳の空気流通を確保し、滲出液を排出・再発を防止します。手術は小児の場合、全身麻酔で行う必要がありますが、短時間で終了し入院期間も数日程度と負担の少ないものです。
耳垢栓塞(耳あかの詰まり)
耳掃除はご家庭でされていますか? 小さなお子さまは耳掃除を嫌がることも多く、綿棒で掃除しようとしてもうまくいかないことがあります。それどころか、奥に耳あかを押し込んでしまい耳垢栓塞(じこうせんそく)という状態を引き起こすことがあります。耳垢栓塞になると耳の穴がふさがってしまい、聞こえが悪くなるため日常生活にも支障が出ます。
原因・症状: 耳垢栓塞は、耳垢(耳あか)が外耳道を塞いで塊になった状態です。耳垢には乾燥したカサカサのタイプと、湿った粘いタイプがありますが、特に湿った耳垢の子は溜まりやすく固まりやすい傾向があります。本来、耳の皮膚には古い耳垢を外に運び出す自浄作用があります。しかし耳掃除をしようとして綿棒を奥まで入れすぎたり、頻繁に耳をいじったりすると、かえって耳垢を奥へ押し込んで蓄積させてしまいます。その結果、耳垢が塊となって耳の通り道を塞ぎ、難聴(伝音難聴)や耳の閉塞感を引き起こします。ひどい場合には耳垢の裏で炎症を起こし、耳だれや耳の痛み、悪臭を伴うこともあります。お風呂上がりに急に聞こえが悪くなる場合も、耳垢が水分を吸って膨張した耳垢栓塞が原因のことがあります。
治療法: 耳垢栓塞の治療は耳鼻咽喉科での耳垢除去が基本です。専用の器具(耳垢鉗子や吸引器)を使えば、こびりついた耳垢も安全に取り除くことができます。小さなお子さんの場合、動くと危険なためしっかり体を固定して行いますが、当院ではお子さまに声かけし安心させながら短時間で処置を終えるよう心がけています。
耳垢が非常に硬くこびりついている場合は、数日間、耳垢を柔らかくする薬液(耳垢溶解剤)を点耳してから再度除去を試みることもあります。一度耳垢を取ってしまえば聞こえはすぐに回復しますが、再発予防のためにもご家庭では無理に耳かきをせず、入浴後に外側を軽く拭う程度に留めましょう。耳垢がたまりやすい体質のお子さまは、定期的に耳鼻科でチェックを受けると安心です。
当院の対応: 当院では、耳垢栓塞による難聴が疑われるお子さまには、その日のうちに耳垢の除去を行っています。小さなお子さまの場合、泣いて暴れてしまうこともありますが、看護師と協力して安全に配慮しつつ処置しますのでご安心ください。耳掃除だけの受診も大歓迎です。「耳あかが奥に見えて心配」「耳そうじを嫌がってできない」という保護者の方は、お気軽に当院にご相談ください。
外耳炎(耳の穴の感染症)
お子さまが「耳が痛い」と訴えるとき、中耳炎以外に外耳炎の場合もあります。外耳炎は耳の穴(外耳道)の皮膚が炎症を起こした状態で、いわゆる「耳の入り口の感染症」です。耳をいじる癖がある子や、プールの後に耳が痛くなった場合などに起こりやすいトラブルです。
原因・症状: 外耳炎は、外耳道の皮膚に傷がついたり水が溜まったりすることで、細菌が繁殖して起こります。例えば綿棒や指で耳を頻繁に触ることで小さな傷ができたり、シャンプーやプールの水が耳に入って湿った状態が続いたりすると、菌が増えやすくなります。症状の特徴は耳介や耳の入口を触ったときの強い痛みです。
中耳炎と違い顎を動かしたときや耳たぶを引っ張ったときにも痛みが走る場合、外耳道の炎症を疑います。また、耳がかゆくなったり、腫れて耳穴が狭くなり聞こえが悪く感じることもあります。進行すると黄色い耳だれが出たり、耳の周囲が腫れて熱を持つこともあります。
治療法: 外耳炎の治療ではまず耳の中の清潔を保つことが大切です。耳鼻科では細い吸引器や綿棒で耳の中の膿や汚れを取り除く処置を行います。
清掃後、抗菌薬の軟膏を耳の中に塗布したり、必要に応じて抗生物質の点耳薬(耳にさすお薬)を処方します。
ご家庭では治療中は耳を濡らさないように注意し、お風呂の際は耳栓や防水テープで耳を保護していただきます。かゆみが強い場合は抗アレルギー薬の内服を併用することもあります。通常、数日から1週間程度の治療で痛みや腫れは改善しますが、途中でよくなっても自己判断で処置を中断せず完治するまで通院しましょう。
はなの疾患
アレルギー性鼻炎(子どもの花粉症・鼻アレルギー)
くしゃみや鼻水が長引く場合は、アレルギー性鼻炎かもしれません。 春先に毎年お子さんの鼻水・鼻づまりや目のかゆみがひどくなる場合は花粉症の可能性があります。また、季節に関係なくほこりっぽい環境でクシャミが出る場合はダニやハウスダストによる通年性のアレルギー性鼻炎が疑われます。近年、小児の花粉症が増えており、小さいうちからアレルギー対策を行うことが重要になっています。
原因・症状: アレルギー性鼻炎は、花粉・ハウスダスト・カビ・ペットの毛などのアレルゲンに対して体の免疫反応が過敏に起こることで、生じる鼻粘膜の炎症です。原因物質はお子さまによって様々ですが、春はスギ・ヒノキ、秋はブタクサなどの花粉、通年ではダニの死骸やハウスダストが代表的です。症状としてはくしゃみの連発、水のような鼻水、鼻づまりが三大症状です。
これに加え、目のかゆみや充血、喉の違和感、皮膚のかゆみを伴うこともあります。小さいお子さんだと上手に鼻をかめずにズルズルと鼻水が出続け、夜間も鼻づまりで苦しくて起きてしまうことがあります。アレルギー性鼻炎を放置すると、慢性的な鼻づまりにより睡眠不足や口呼吸の癖がつく原因となり、お子さまの集中力や食欲低下にもつながりかねません。
治療法: アレルギー性鼻炎の治療は、薬物療法と環境調整が中心です。まず、花粉やハウスダストとの接触を減らす工夫(マスクの着用、室内のこまめな掃除・換気、寝具の洗濯など)を行いましょう。その上で症状に応じてお薬を使用します。主に用いるのは抗ヒスタミン薬(くしゃみ・鼻水を抑える飲み薬)やステロイド点鼻薬(鼻粘膜の炎症を直接抑える噴霧薬)です。小児用の抗ヒスタミン薬は眠くなりにくい種類もあり、年齢や症状に合わせて使い分けます。鼻づまりが強い場合は抗ロイコトリエン薬という飲み薬や点鼻薬を併用して改善を図ります。
季節性の花粉症で毎年症状が重いお子さんには、舌下免疫療法(スギ花粉やダニに対する体質改善療法)も検討します。これはスギ花粉症の場合5歳以上から適応となり、毎日舌の下にアレルゲンのエキスを含ませる治療で、数年かけて花粉症を和らげる方法です。
副鼻腔炎(蓄膿症)
風邪の後に鼻水や咳が長引いているときは要注意です。 普段は元気なお子さんでも、感冒後に黄色い鼻水がいつまでも続いたり、夜間に痰の絡んだ咳をしている場合は小児副鼻腔炎を起こしている可能性があります。「風邪自体は治ったのに鼻づまりだけ残っている」というお子さんが多く来院されますが、その多くは副鼻腔炎(いわゆる蓄膿症)と診断されています。
原因・症状: 副鼻腔炎とは、鼻の周囲にある副鼻腔(空洞)が細菌感染などで炎症を起こし、膿が溜まった状態です。子どもの場合、大人より副鼻腔の発達が未熟ですが、上顎洞や篩骨洞といった空洞は乳幼児期から存在するため、風邪をきっかけに副鼻腔炎になることがあります。典型的な症状は鼻汁の性状悪化です。初めはサラサラだった鼻水が風邪の後期に黄色~緑色の粘い鼻水に変わり、それが10日以上続きます。鼻づまりも強くなり、嗅覚(においを感じる力)が落ちることもあります。また、鼻水が喉にまわるため湿った咳が長引くのも特徴です。
小児の場合、大人のような頬の痛みや頭痛を訴えることは少ないですが、乳幼児では鼻詰まりのせいで授乳や食事がうまくできず元気がない、といった変化が見られることもあります。熱は副鼻腔炎に移行する時点では下がっていることも多いですが、細菌感染が広がると再び発熱したり、目の周囲が腫れるといった合併症(まれですが眼窩蜂窩織炎など)のリスクもあります。
治療法: 小児副鼻腔炎の治療は、まず内科的治療(お薬と処置)を十分に行うことが基本です。具体的には抗生物質の内服を1~2週間程度続け、鼻水の細菌を退治します。あわせて耳鼻科では鼻汁の吸引やネブライザーによる抗菌剤・消炎剤の吸入など局所治療を行います。ネブライザーとは薬をミスト状にして鼻や喉の粘膜に届ける治療で、小さなお子さんでも痛みなく受けられます。これにより副鼻腔内の膿を出しやすくし、粘膜の腫れを和らげます。
症状が改善してきたら抗生剤を減らしつつ、鼻炎が残る場合は粘膜を整える抗アレルギー薬や漢方薬を用いてケアします。副鼻腔炎は再発・遷延しやすい病気のため、治りかけでも油断せず処方されたお薬は指示通り最後まで飲み切りましょう。
なお、小児では副鼻腔の発達が未熟なため手術治療は原則行いません。慢性化してどうしても治らない場合は大きくなってから内視鏡手術を検討することもありますが、多くは成長とともに改善します。
アデノイド肥大(鼻の奥の扁桃の肥大)
お子さまが常に口で呼吸していたり、いびきがひどい場合は、鼻の奥にあるアデノイド(咽頭扁桃)が大きくなっている可能性があります。アデノイドが肥大すると鼻の奥の空気の通り道が狭くなり、鼻づまりやいびき、睡眠時の無呼吸の原因となります。当院でも、豊島区・板橋区エリアのお子さまの「いびきが心配」「夜中に呼吸が止まることがある」といったご相談を多く受けていますが、原因としてアデノイド肥大が見つかるケースが少なくありません。
原因・症状: アデノイド(咽頭扁桃)は鼻の突き当たり、喉との境界付近(上咽頭)にあるリンパ組織で、いわば鼻の奥の扁桃腺です。幼少期に一時的に大きくなりやすい特徴があり、3~6歳頃に肥大のピークを迎え、その後思春期までに小さくなることが多いです。
アデノイドが大きく肥大化すると、鼻の奥の空間を占領してしまうため慢性的な鼻づまりを引き起こします。その結果、お子さんは口で呼吸する癖がつき、夜間には大きないびきをかきます。進行すると睡眠中に呼吸が一時的に止まる睡眠時無呼吸症状群の原因にもなり得ます。また、アデノイドは耳の通り道である耳管のすぐ近くに位置するため、肥大により耳管が圧迫されると滲出性中耳炎の原因になったり、何度も中耳炎を繰り返す要因ともなります。
日中でも鼻声(鼻にかかった話し方)になったり、匂いが分かりにくい、食事のときにくちゃくちゃ音がする(口で呼吸しているため)といった症状が見られることもあります。さらに口呼吸が続くことで喉が乾燥しやすくなり、風邪や咽頭炎にかかりやすくなる悪循環も懸念されます。
治療法: アデノイド肥大への対応は、お子さまの年齢と症状の程度によって異なります。症状が軽度であれば成長とともに縮小する可能性が高いため、経過観察とします。この間、風邪をひいてアデノイドが炎症を起こしているような場合には、抗生物質やステロイドの点鼻などで一時的に腫れを抑え、症状を緩和します。また、鼻づまりに対してはアレルギー性鼻炎の治療と同様に点鼻薬やネブライザーで鼻粘膜の状態を整えます。
一方、症状が重度(夜間の無呼吸が顕著、言葉の発達遅延や日中の集中力低下がみられる等)で日常生活に支障をきたす場合や、中耳炎を繰り返している場合には手術的治療が選択肢となります。アデノイド摘出術は全身麻酔下で口から器具を入れてアデノイドを切除する手術です。同時に近くの口蓋扁桃(扁桃腺)も大きい場合は一緒に摘出することもあります。入院が必要ですが1週間程度で退院でき、手術後は嘘のように鼻通りが良くなり、いびきや無呼吸が改善するケースがほとんどです。
鼻閉(子どもの鼻づまり)
鼻づまり(鼻閉)は小児でよく見られる症状の一つですが、その原因は様々です。単なる風邪による一時的な鼻づまりから、アレルギー性鼻炎やアデノイド肥大による慢性的な鼻づまりまで幅広く存在します。特に乳児は自分で鼻をかむことができないため、少量の鼻水でも詰まってしまい苦しくなります。鼻でうまく呼吸ができないと、おっぱいやミルクが飲めない、夜眠れないといった問題が生じ、保護者の方にとっても大きな不安となります。
原因・症状: 子どもの鼻閉の主な原因としては、まず急性鼻炎(風邪)があります。風邪をひいて鼻水が出るとき、幼児は上手に鼻をかめず鼻汁が残りやすいため、長引く鼻づまりに発展しがちです。また前述のアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎でも慢性的な鼻づまりが起こります。さらに、アデノイド肥大や鼻の粘膜の肥厚(鼻甲介肥大)など構造的な問題で常に鼻が詰まっているケースもあります。症状としては、鼻呼吸がしにくいため口で呼吸する癖がつく、夜間にいびきをかく、食事のときにむせやすい、声が鼻声になる、といったものがあります。乳児の場合は鼻が詰まるとおっぱいを飲みながら息ができず何度も途中で離してしまう、苦しくて泣いてしまう、といったサインで気づきます。長期間口呼吸が続くと口腔内が乾燥して虫歯や喉の感染にかかりやすくなるほか、顎の発達や歯並びにも影響すると言われていますので、慢性的な鼻閉は軽視できません。
治療法: 鼻閉の治療は原因に応じた対処が基本です。風邪が原因なら風邪の治療を、アレルギーが原因ならアレルギー治療を行います。急性期の鼻づまりに対しては、一時的に血管収縮薬の点鼻(鼻粘膜の腫れをひかせる即効性のスプレー)を使うことがありますが、長期間の使用はできないため数日間に留めます。小さなお子さんには市販の生理食塩水の点鼻も効果的です。鼻の中を洗い流してあげることで粘膜が潤い、粘ついた鼻汁が取れやすくなります。また、室内の適度な加湿も鼻づまりの緩和に役立ちます。アデノイドや鼻中隔の構造的な問題が大きい場合は手術的治療も選択肢になりますが、成長とともに改善する場合も多いので、小児期はできるだけ薬や生活指導で乗り切ることが一般的です。
のどの疾患
扁桃肥大(扁桃腺が大きい)
お子さまの扁桃腺(口蓋扁桃)が大きいと感じたことはありませんか?鏡で喉を見ると両側にあるコブ状の組織が扁桃ですが、これが肥大すると喉の通り道が狭くなり、様々な症状を引き起こします。扁桃肥大は小学生くらいのお子さんに多く、一見元気でもいびきや無呼吸の原因となっていることがあります。
原因・症状: 扁桃(扁桃腺)は免疫を担うリンパ組織で、外から入る菌やウイルスと戦う重要な場所です。小児期には活発に働くため一時的に大きくなる傾向があります(思春期頃に小さくなることが多いです)。しかし、元々の大きさが目立つ場合や何度も扁桃炎を繰り返すことで扁桃組織が腫れたままになっている場合、扁桃肥大と呼ばれる状態になります。症状としては、喉の空間が狭くなるため睡眠時の強いいびきや無呼吸発作が現れます。
特に扁桃とアデノイドが両方肥大していると、上気道が著しく狭くなるため夜間の呼吸障害が顕著です。また扁桃が大きいと食べ物が喉を通りにくく飲み込みづらさを訴えたり、声がこもって聞き取りにくい話し方になることもあります。
さらに、扁桃肥大の背景として慢性扁桃炎がある場合、年に何度も喉の強い痛みと高熱を繰り返す(扁桃炎発作)という問題が起こります。学童期に溶連菌感染症などに度々かかっているお子さんは、扁桃が常に腫れて肥大しているケースが多いです。
治療法: 扁桃肥大そのものを小さくする薬はありませんので、基本的には経過観察と症状への対症療法となります。肥大があっても普段の生活に支障がなければ経過を見ます。
一方、睡眠時無呼吸がひどい場合や扁桃炎を年に何度も繰り返す場合には、手術による治療を検討します。扁桃摘出術は全身麻酔で口蓋扁桃を両側とも摘出する手術です(先述のアデノイド摘出術と同時に行われることもあります)。手術直後は喉の痛みがありますが、1~2週間で回復し、以後は明らかにいびきや喉の痛みの頻度が減ります。小児では成長への影響を考え、無呼吸が重度な場合や年間数回以上の扁桃炎エピソードがある場合などに手術適応となることが多いです。手術以外では、扁桃炎を起こした際に抗生物質でしっかり治療する、うがい・手洗いで予防する、といったことが重要です。
咽頭扁桃炎(喉の炎症)
喉が赤く腫れて痛む状態は総称して咽頭炎と呼ばれます。小児の咽頭炎の多くはウイルス感染に伴うものですが、中には細菌が原因で高熱を出すものもあります。特に学童期のお子さんでは、溶連菌(ようれんきん)という細菌による咽頭炎(いわゆる「溶連菌感染症」)がよくみられます。
原因・症状: 咽頭炎の原因の大半はウイルス感染です。いわゆる風邪症候群の一部として喉の炎症が起こり、喉の痛み、発熱、せき、鼻水など複数の症状を伴います。代表的なウイルスとしてはアデノウイルス、コクサッキーウイルス、ライノウイルスなど数多く、特にアデノウイルス感染症では高熱とひどい咽頭炎が特徴的です。
一方、溶連菌など細菌が原因の咽頭炎は、猛烈な喉の痛みと高熱が主症状で、鼻水や咳などはあまり見られません。扁桃に白い膿がついたり、首のリンパ節が腫れることもあります。小児では機嫌が悪く元気消失し、水分すら飲み込めなくなることもあります。咽頭炎全般で共通する症状として、喉の痛み以外に飲み込みづらさ、声が枯れる、口臭がする、といったことがあります。乳幼児の場合、喉が痛くても訴えられないので、食事や授乳のときに泣いて拒否する、よだれが増える、といった様子で気づくことがあります。
治療法: 咽頭炎の治療は原因によって異なります。ウイルス性咽頭炎の場合、特効薬はなく症状を和らげる対症療法が中心です。十分な水分補給と栄養・睡眠をとり、安静に過ごすことが大切です。喉が痛くて飲み込めない場合は無理に固形物を食べさせず、ゼリーやスープなど喉ごしの良いもので水分・エネルギー補給します。年長のお子さんであればうがいをさせたり、痛み止めの薬を使用することもあります。
細菌性咽頭炎と診断された場合は、抗生物質の内服が必要です。特に溶連菌感染症は放置するとリウマチ熱や腎炎などを合併する恐れがあるため、10日間程度の十分な抗生剤投与で細菌を根絶します。発熱が高いときは解熱鎮痛剤を使用し、安静を保ちます。いずれの場合も、周囲への感染を防ぐため手洗いやマスクの着用を心がけましょう。
喉頭炎(クループ症候群)
夜間に突然「ケンケン」という咳をし始め、呼吸が苦しそうになった—そんな症状が現れたらクループ症候群(急性喉頭炎)かもしれません。クループは主に乳幼児(1~5歳)に起こる喉頭(声帯やその下の部分)の炎症で、喉の奥が狭くなって呼吸困難をきたすことがあります。保護者の方にとって、夜中にお子さんが喘ぐような咳をして息苦しそうにしている姿は非常に心配なものです。
原因・症状: クループ症候群の多くはウイルス感染が原因です。パラインフルエンザウイルスが代表ですが、他にもRSウイルスやアデノウイルス、インフルエンザウイルスなど様々なウイルスが喉頭の粘膜に感染し、声帯周囲がむくんで空気の通り道が狭くなります。典型的な症状は、犬が吠えるような「ケンケン」という乾いた咳」(犬吠様咳嗽)と、息を吸うときに「ヒューヒュー」という音がする喘鳴(ぜんめい)です。声がかすれる嗄声もみられます。これらの症状は夜間から明け方に悪化しやすく、日中は軽度の咳程度ですむこともあります。
発熱は出る場合と出ない場合がありますが、出ても高熱になることは少なく、主な問題は呼吸のしづらさです。軽症であれば息苦しさは軽度ですが、中等症以上になると呼吸がゼーゼー苦しそうになり、肩で息をする、肋骨と肋骨の間や鎖骨の上がペコペコへこむ(陥没呼吸)などのサインが見られます。重症になると唇が紫色になる(チアノーゼ)など命に関わる状態になるため注意が必要です。
治療法: クループ症候群の治療は症状の程度によって異なりますが、気道の確保と炎症を鎮めることが目的です。家庭でできる対処としては、お子さまを落ち着かせてあげることが大切です。泣くと呼吸がさらに苦しくなるため、親御さんがそばで安心させてあげましょう。また、室内を適度に加湿したり、冷たい外気に当てると症状が和らぐことがあります。病院での治療は、呼吸が苦しそうな場合にはネブライザーによるアドレナリン吸入療法を行います。アドレナリン(エピネフリン)には気道の腫れを一時的にひかせる効果があり、吸入後しばらくすると咳や喘鳴が改善します。ただし効果は数時間で切れるため、その間に根本の炎症を抑えるためステロイド薬(デキサメタゾン等)を内服または注射します。ステロイドは数時間かけて効果が現れ、喉頭のむくみをしっかりと鎮めてくれます。
軽症であればこの治療を外来で行い帰宅となりますが、改善が不十分な場合や夜間に再発するリスクが高い場合は入院治療となることもあります。入院時は酸素投与や点滴を行いながら経過を見ます。幸い、ウイルス性クループは適切に対処すれば数日で良くなることがほとんどです。
抗菌薬(抗生物質)の使用について
子供は大人に比べて体力が弱いことや、上手く表現ができないため、症状を早期に抑えてあげたいと考えています。
そのため抗菌薬の適応がある場合は処方し、早期の症状改善を目指します。
ただし、抗菌薬はウイルス性の病気には効果が無く、細菌性の病気でも細菌の種類と抗生剤の種類によっては効果の有無が異なりますので、何らかの感染が疑われる場合は菌の種類を特定する検査を積極的に行い、無用な抗生剤の使用はしないように心がけています。
実際の診察にあたっては、「抗菌薬を使用して欲しい」「抗菌薬はできる限り使用して欲しくない」というような保護者の方のご希望も伺った上で、医師として処方を決定しますのでご希望がある場合はお申し出ください。
鼻吸い(鼻水の吸引)について
大人も子供も鼻と耳が耳管という管で繋がっています。子供は成長段階にあるため耳管が太く、傾きもゆるやかなため、風邪などをひいた時に鼻やのどにいる細菌が耳管を通って耳に入りやすく容易に中耳炎にかかります。
また、鼻水は子供の長引く咳の原因になります。子供は鼻を上手くかめないため鼻水が喉に垂れていき、咳を誘発します。夜になると痰がからむ咳が目立つ場合はぜんそく以外に鼻水による咳が疑われます。
お子さまが鼻水を出している時は積極的に鼻の吸引をしてあげることで鼻づまり、咳などの症状が楽になる上、中耳炎などへの移行のリスクも抑えられるので鼻水を吸ってあげるようにしてください。
当院でも鼻水の吸引を行っておりますがこまめに吸引することで子供が楽になるため、保護者の方の通院の負担を考え、ご自宅でも吸引をしていただくことをお勧めしております。
鼻水を頻繁に出している子供は風邪以外にアレルギー症状として鼻水が出ているケースが良くあります。最近では幼小児の花粉症患者さんもめずらしくなくなりました。
アレルギーがある場合はアレルギーの原因(アレルゲン)を調べて日常生活からアレルゲンを取り除くことでずいぶんと楽に過ごせるようになるのですが、子供の場合注射器や採血を怖がってしまってなかなか調べられないことが多いように感じます。
当院では調べられるアレルゲンは限られるものの、注射器を使わず指先からの採血ですぐに結果がわかる検査も導入しておりますので、お子様が年に何回も鼻水を出している場合はご相談ください。
注射器を使わず指先からの採血で当日に結果がわかる検査について
お子様の診察時の注意点について
耳鼻咽喉科では多くの処置を行います。処置は、内服薬以上に効果を示す場合があります。特に、お子さんは急性中耳炎、急性副鼻腔炎を起こしやすく、耳、鼻処置が必要です。処置に際しては細心の注意を払って行っており、なるべく怖がられないような対応を心がけております。しかしお子様からすれば慣れない処置は怖いものですので、どうしても動いたり、暴れたりしてしまうことがあります。
泣いている子供をおさえるのはかわいそうとの気持ちは当院でも同じではございますが、やさしくおさえた結果、思わぬ事故に繋がってしまう可能性も秘めております。当クリニックでは、処置の必要性を十分理解していただいた上、安全に処置を受けて頂けるように努めています。親御様におかれましては、下記のようにお子様の固定にご協力をお願いできれば幸いです。診察時にスタッフからもお願いさせていただきます。

上のように親御さんに椅子に座っていただき、膝の上にお子様を座らせます。親御さんはお子様を上から包み込むように固定してくださるようお願いしています。