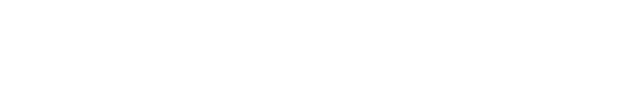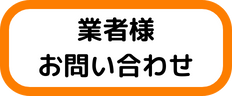風邪(かぜ)は何科?症状や治療法を解説!
風邪とは何か?
そもそも風邪とはどういったものを指すのでしょう?。風邪という言葉があまりに一般的すぎて、ヒトによって解釈が少しずつ異なるのと、患者さんが言う「風邪」と医師が考える「風邪」には多少の違いがあるかもしれません。
風邪は、正式には「風邪症候群」といい、一般的にくしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、たん、発熱などを引き起こす急性の上気道感染症のことです。風邪は、80~90%はウイルスによって引き起こされる感染症の一種であり、空気中に浮遊しているウイルスや細菌などの病原体が気道内に入り、炎症を起こすことで始まります。ウイルスはおよそ200種類以上存在しているため、原因のウイルスを特定することは容易ではありません。
ライノウイルスが最も多く30~40%を占め、次いでコロナウイルス(10~15%)、インフルエンザウイルス(5~15%)、RSウイルスとパラインフルエンザウイルス(5%)、アデノウイルス、エンテロウイルスが続きます。アデノウイルス、ライノウイルスは春と秋に多く、夏季はエコーウイルス、コクサッキーウイルス、エンテロウイルス、冬季はRSウイルス、インフルエンザウイルスが多いです。
ちなみにウイルス感染以外のものですと、一般細菌(溶連菌など)、マイコプラズマ、クラミジアなどがあります。
風邪は、季節性のものや流行性のものがあり、多くの人が感染することがあります。風邪の症状は、免疫力の低下やストレス、疲れなどによって引き起こされることがあります。
風邪のウイルスは、主に空気中の飛沫や手などを介して感染が拡大します。感染後、ウイルスは鼻や喉などの粘膜に付着し、細胞内に侵入して増殖し、そのウイルスを排除しようとする免疫反応が起こります。この免疫反応によって、体内で炎症が起こり、風邪の症状が現れます。
症状は感染するウイルスの種類によってもさまざまですが、同じウイルスでも感染した人によっても症状の出方は千差万別です。例えば有名なインフルエンザウイルスに感染しても発熱しない方もいらっしゃいますし、軽度の鼻水のみで治ってしまうこともあります。医師が「風邪ですね」というと、「え?でも鼻みずだけで熱もないですし」といわれることが少なくないのですが、風邪=発熱ではありません。
症状が限定的な場合は、「鼻風邪ですね」や「のど風邪ですね」とお伝えするようにしていますが、医学的には「風邪症候群」として同じ分類に分けられます。
▶︎耳・鼻・喉の辛いは池袋ながとも耳鼻咽喉科へご相談ください!カンタンWeb予約はこちら
『風邪』は何科を受診すればよいか?

結論としては内科でも耳鼻科でもどちらを受診しても大丈夫です。一般的には、「風邪をひいたかも…」と感じて受診先を探すとき、まず思い浮かべるのは、内科という方が多いと思います。
一方で、耳鼻科でも初期から風邪を診ることをご存じでしょうか。耳鼻科では、鼻だけでなく、喉(咽頭・喉頭)までファイバースコープにより直接観察することができます。粘膜の炎症や膿の状態、腫れの程度が正確に分かり、そうして得た確かな情報をもとに治療を行うことができます。鼻水の吸引、洗浄も受けられますので、その場での症状の緩和という意味でも強みがあります。
風邪の症状の大部分は鼻汁、咽頭痛、咳などのいわゆる上気道炎ですから、耳鼻咽喉科が最も得意とする得意領域です。実際、最初に内科を受診して良くならないから耳鼻科に来ました、という方も少なくありません。
ポジショントークになってしまいますが、後述する風邪に続発した合併症(中耳炎、副鼻腔炎、扁桃炎など)のケアも踏まえると、初期の風邪の段階で、耳鼻科を受診していただくメリットは十分にあると思います。
▶︎風邪は耳鼻科で鼻や喉の症状を相談!池袋ながとも耳鼻咽喉科のカンタンWeb予約はこちら
風邪で耳鼻科を受診するメリット
①風邪の症状のほとんどは、みみ・はな・のどに集中している
風邪の症状は以下に示しますが、ほとんどがみみ・はな・のどに集中しています。風邪ウイルスや細菌のほとんどは空気や飛沫、接触によってヒトに感染するため、それらを最初に取り込む部位が顔にあるからです。体に侵入したウイルスや細菌は入口近くの粘膜に感染し炎症を起こし、症状を発生させます。ですので、みみ・はな・のどの症状が初期症状としても重篤な症状としても出現しやすいのです。それらの症状を専門として診ているのは耳鼻科ですので、耳鼻科こそ風邪のスペシャリストといえるのです。
▶︎風邪は耳鼻科で鼻や喉の症状を相談!池袋ながとも耳鼻咽喉科のカンタンWeb予約はこちら
②「耳鼻咽喉科専門医」がきちんと検査、処置を行う
耳鼻咽喉科には、鼓膜をみる機械、鼻の奥やのどの奥をみるファイバースコープ、レントゲン、CTなどの機械がそろっています。また、多くの症例を経験していますのでそれらを駆使して必要な検査をする「カン」を普段から養っているといえます。
③副鼻腔炎や中耳炎などの合併症の対応ができる
後述するように、初期は風邪であっても改善しない場合には副鼻腔炎や中耳炎を併発してしまうことがあります。その際も、まさに専門領域ですので診断と治療を行うことができます。
また、時には急性喉頭蓋炎や扁桃周囲膿瘍など生命に危険が及ぶ合併症もあり、診断にはファイバースコープが必要となります。
④お子さまの鼻みず吸引ができる
お子さまの風邪で最も多い症状は鼻水です。大人のように上手に鼻をかむことができず、また解剖学的に鼻腔が小さいため中に長期間溜まった鼻汁に細菌が感染して副鼻腔炎を発症しやすいのです。ご自宅での吸引も重要ですが、耳鼻咽喉科では専用の機械で奥まで吸引することができますし、必要に応じてネブライザー療法も行うことができます。
風邪の症状
風邪の症状は、ウイルスの種類や個人差によってさまざまですが、上気道の局所症状として・呼吸器症状として鼻汁、鼻閉、咽頭痛、咳、痰など、全身症状として悪寒、発熱、頭痛、倦怠感、関節痛などが出現します。悪心、嘔吐、下痢などの消化器症状を示すこともあります。
鼻水、鼻づまり
風邪による鼻水や鼻閉は、風邪の初期症状として現れることが多く、感染による鼻粘膜の炎症が原因です。炎症が鼻粘膜を刺激し、鼻水が出たり、鼻腔が狭くなって鼻閉を起こします。
鼻水は、風邪の初期段階から症状が現れることがあります。鼻水は、風邪のウイルスや細菌などによって引き起こされた炎症が原因で、鼻粘膜から出る液体です。一般的には風邪が治癒するにつれて鼻水も減少していきますが、鼻水が緑色や黄色になったりすると副鼻腔炎を併発している可能性があるので注意が必要です。
鼻閉も鼻水と同様に風邪の初期段階から現れることがあります。鼻粘膜の炎症によって、鼻腔の内側の血管が膨張し、鼻腔が狭くなって鼻閉を引き起こします。鼻閉は、風邪の症状の中でも比較的長期間続くことがありますが、多くの場合、風邪が治癒するとともに改善されます。
のどの痛み
風邪による咽頭痛は、のどの奥や喉の表面に炎症が起こったことによって引き起こされます。のどが痛むだけでなく、喉の奥が詰まっているような感覚や、喉の乾き感、イガイガ感、痒みを伴うことがあります。また、咳や痰、発熱、倦怠感などの風邪の症状が同時に現れることもあります。
咳
風邪による咳は、風邪ウイルスが気道や喉の粘膜に感染して炎症が起こったり、粘液がたまっているために引き起こされます。咳は、気道に異物が入った際に起こる自然な防御反応であり、喉や気道を刺激することで異物を追い出すためのものです。風邪による咳も同様で、炎症や粘液が気道や喉に刺激を与えて咳を引き起こすとされています。
風邪による咳は、乾いた咳や痰を伴う咳など、種類によって異なります。乾いた咳は、喉の痛みや炎症が原因で発生し、喉がイガイガするような感覚を伴います。一方、痰を伴う咳は、気道にたまった粘液を排出するための咳で、風邪の症状の中でも特に長引くことがあります。
風邪による咳は、通常数週間から1か月程度で治まりますが、長引く場合や痰が黄色や緑色に変色する場合は、細菌感染が原因となっている可能性があるため、診察が必要です。
また、喘息をお持ちの方は注意が必要で、上気道のウイルス感染で喘息症状が誘発されたり、病気が悪化したりすることは古くから良く知られています。
発熱
風邪による発熱は、感染したウイルスの種類や感染する宿主(個人)によってさまざまです。ほとんどは37~38℃程度で治まりますが、インフルエンザなどでは40℃近くになることもありますが、一般的には1週間以内で治まります。
発熱により、体内の免疫細胞が活性化し、ウイルスや細菌などの病原体に対して戦うための免疫反応が促進されます。そのため、一般的には風邪による発熱は、体内の免疫力を高めるために必要なものとされています。
熱があるからといって、必ずしも解熱剤ですぐに熱を下げる必要はありません。熱の割には体は元気で、食欲もある場合は様子をみても大丈夫です。一方で、解熱する必要がある状況は、体がだるくつらい場合や、体温が高いままでいると脱水を引き起こす危険性のある高齢者や乳幼児などの場合はまた、熱が出た場合は、十分な水分補給を心掛けましょう。
発熱による注意点としては、体温が高いままでいると、脱水症状を引き起こすことがあります。そのため、こまめに水分補給を行うことが大切です。また、熱が高い場合は、冷たいタオルなどで身体を冷やすことも有効です。ただし、急激な体温変化は身体に負担をかけるため、冷やしすぎには注意が必要です。
音声障害(声がれ)
風邪によって声が出なくなることを経験したことがある方は少なくないと思います。多くは、声帯に急性の炎症が加わったことによる声帯粘膜や粘膜下組織の障害が原因で、声帯の振動が乱れます。また、のど全体が腫れることによって、鼻腔や上咽頭の共鳴腔が狭くなってしまい、音が響かない(鼻が詰まったような声になる)ことも原因です。
風邪による声がれに対する特別な治療方法はなく、声の安静、十分な水分摂取と加湿、禁煙などが重要です。無理な声の使用は、声帯の瘢痕化などの深刻な事態を招く可能性があるため、特に声の使用が背景にある場合はには発声を控えるようにした方がよいです。
筋肉痛や関節痛
風邪による筋肉痛は、全身的な痛みを感じることがあります。肩や腰などの大きな筋肉群が痛みや疲労感を感じることが多く、多くの場合は数日から1週間程度で自然に治まります。
風邪による関節痛は、手足の指や膝などの関節部分に痛みや腫れが生じることがあります。また、炎症が関節液に及ぶことで、関節の動きが制限される場合もあります。
筋肉痛や関節痛は、風邪の初期症状として現れることが多く、多くの場合は数日から1週間程度で自然に治まります。
腹痛、下痢
風邪の症状としては、主に鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、発熱などが挙げられます。しかし、お腹の症状である腹痛や下痢が風邪の症状として現れることもあります。
風邪は、ウイルス感染症であり、一般的には上気道症状が主な症状とされています。しかし、風邪のウイルスは消化器系でも増殖するため、お腹の症状が出る場合があります。具体的には、下痢、腹痛、吐き気、嘔吐、食欲不振などが挙げられます。このような症状がある場合は、耳鼻咽喉科よりも内科の受診をお勧めいたします。
風邪の治療
安静、水分・栄養補給により自然に治癒するため基本的には自宅療養となります。かぜ症候群は、一般的には自然治癒するものであり、薬でウイルス感染を治療できるわけではありません(インフルエンザなど一部のウイルス感染を除きます)。
解熱鎮痛剤、咳止め薬、痰きり薬、うがい薬、漢方薬などにより対症療法を行います。
しかし、以下に様な細菌感染を背景とした合併症が疑われる場合は、抗生物質を処方します。
風邪が引き起こす合併症

中耳炎
中耳炎は、鼓膜の奥の空洞である中耳に炎症が起きる病気です。中耳は耳管という管で鼻の奥の上咽頭とつながっているため、鼻風邪やのど風邪を引くことによって増殖したウイルスや細菌が、耳管を介して中耳に侵入し感染を起こすのです。特に、子供は中耳炎にかかりやすく、重症化することもあります。
副鼻腔炎(ちくのう症)
副鼻腔炎は、鼻の奥にある副鼻腔の内部に炎症が起こる病気です。風邪やアレルギーなどによって、副鼻腔に詰まった粘液が細菌の繁殖を招き、炎症を引き起こすことがあります。主な症状としては、鼻づまり、頭痛、顔面の圧迫感、痰が出るなどが挙げられます。
副鼻腔炎は、症状が軽いうちに耳鼻咽喉科を受診し、適切な治療を受けることが大切です。
副鼻腔炎は、治療が適切に行われないと慢性化し、再発することがあります。そのため、正しい治療法を受けることが大切です。また、副鼻腔炎の予防には、風邪やアレルギーを引き起こす原因を避けることや、空気の乾燥を防ぐために加湿器を使用することが有効です。
扁桃炎
扁桃炎は、扁桃(口蓋扁桃)がウイルスや細菌感染によって炎症を起こすことを言います。ほとんどの場合でのどの痛みを訴え、時に発熱や関節痛なども引き起こします。扁桃炎は重症化すると扁桃周囲膿瘍となり、切開排膿が必要になったり入院して点滴の治療が必要になることもあります。また、繰り返し扁桃炎を起こす反復性扁桃炎では手術治療が選択されることもあります。扁桃炎の正確な診断は、のどを見慣れている耳鼻咽喉科に相談した方が良いと思います。
肺炎
風邪が原因で、肺炎が合併することがあります。肺炎は、肺の組織に炎症が生じることで、発熱や咳、息苦しさなどの症状が現れます。高齢者や免疫力の低下した人、基礎疾患を持っている人は、肺炎を発症しやすいため、早期の診断と治療が必要です。
診断には胸部レントゲン写真が必要ですが、ほとんどの耳鼻咽喉科では胸部を撮影する機械がありませんので内科受診をお勧めすることになります。
風邪の予防
かぜはウイルス感染であり、主な感染経路は飛沫感染と接触感染です。風邪の予防には昔からうがい、手洗い、マスクの着用が勧められています。新型コロナ感染症流行により、以前よりもうがい、手洗い、マスクの着用が徹底され、風邪になる回数が減ったと自覚されている方も少なくないと思います。
うがい
日本におけるうがいの風邪予防効果に対するランダム化比較試験が2005年に行われました。387人の成人を「水うがい」「ポビドンヨードうがい」「何もしない」の3群に分けて風邪の罹患率を比較したところ、水うがいが風邪の罹患を40%低下させる結果となりました。ポビドンヨードには殺ウイルス作用がありますが、炎症のない口腔内に使用すると常在菌の破壊、正常組織の傷害の可能性があるため、ポビドンヨードによるうがいは予防のためではなく、風邪に罹患したときに行う方が望ましいと考えられます。
口腔内には常在菌が生息しており、常在菌は外部から侵入する病原微生物による感染を防御しています。常在菌に影響を与えないようにうがいすることが大切であり、予防目的のうがいには水が適していると考えます。
手洗い
上気道炎に対する手洗い、マスク、手袋、ガウン着用などの実際的な介入について検討した67論文のシステマティックレビューがあります(2011 Cochrane Database Syst Rev)。この中では唯一、手洗いが上気道感染の予防効果がありました。
マスク
風邪は飛沫感染であるため、他人にうつさないように咳エチケットは大切です。風邪をひいたときにマスクをつけた方がよいことは言うまでもないでしょう。
予防効果に関しては、様々な見解があります。マスクの着用による風邪予防が有効であるかということに関して、2020年に英国有名誌Lancetにおいて、16か国2万6000人のデータを分析し、マスク、眼の防護、社会的距離が新型コロナウイルスの感染リスクを減少させる効果があることが示されています。マスクの使用により感染リスクが85%減少し、医療現場では3分の1、一般の場所では約半分のリスクになることが明らかになりました。特にN95マスクは96%の効果があります。眼の防護策(ゴーグルやフェイスシールド)を取ることで感染リスクが78%減少すると結論されました。
一方で、マスク着用が風邪予防には寄与しないという論文もあり、マスクが風邪予防に有効だと一言で結論付けるのは難しそうです。
また、睡眠時にマスクを装着することによる風邪症状の軽減効果を検討した日本の報告では、就寝時にマスク着用する群がしない群に比べて、風邪症候群の治癒までの日数や、のどの症状の消退日数が短かったという結果もあります。就寝時は気道分泌量が減少し、嚥下による咽頭クリアランスが低下します。また、口呼吸によって咽喉頭の乾燥が助長され、バリアとなる粘液層が影響を受けます。マスクによる保温、保湿効果は上気道粘膜や扁桃組織に対して、何らかの良い効果があると推察されます。
よくある質問
風邪はどのようにしてうつるのでしょうか?
風邪は、感染した人の咳やくしゃみによって飛沫が放出され、それに触れることで感染することがあります。また、感染した人が触った手や物に付着したウイルスに触れることで感染することもあります。
風邪を予防するためにはどのような対策が必要でしょうか?
風邪を予防するためには、手洗いやうがいをしっかりと行うことが重要です。また、人混みの場所や密室の中に長時間いることは避け、十分な睡眠をとることも大切です。
風邪を引いた場合、どのような治療法がありますか?
風邪の治療法としては、安静にすることや十分な水分補給を行うことが重要です。また、解熱剤や鎮痛剤を使用することで、症状の緩和が図れます。ウイルス性の風邪には抗生物質は風邪には効果がないため、基本的には症状を軽減する対症療法が中心になります。市販の総合感冒薬には、病院で処方される咳止め、鼻止め、痛み止めなどの成分が少しずつ含まれています。
一方で、細菌感染を併発していると判断する場合は抗生物質が有効ですので処方します。
風邪の治療期間はどのくらいですか?
風邪の症状には個人差がありますが、一般的には1週間から10日程度で治まることが多いです。ただし、症状が長引く場合や、高熱や呼吸器症状がある場合には、医師の診察を受けるようにしましょう。