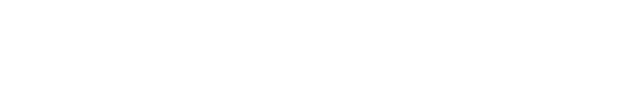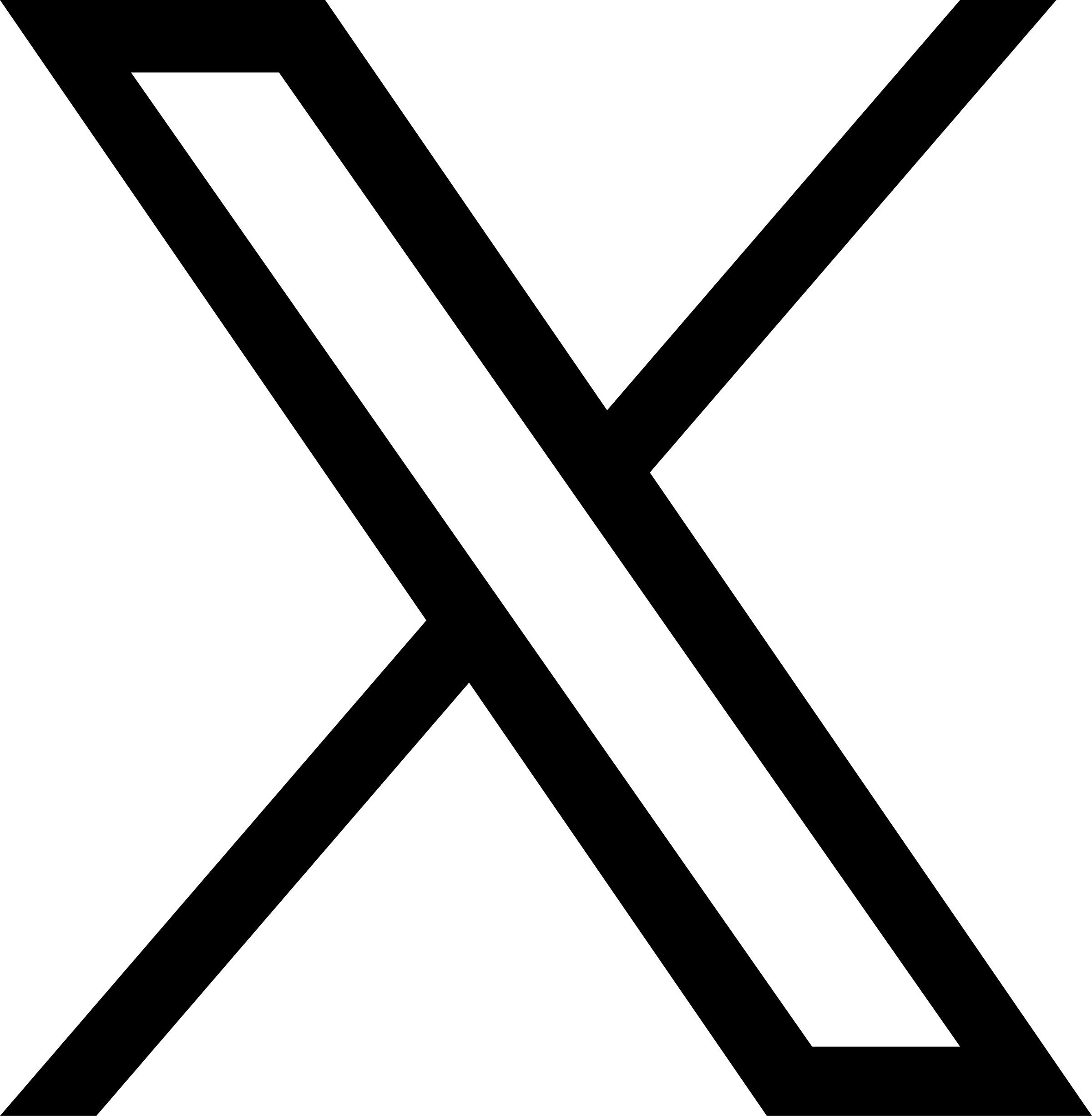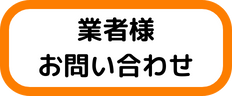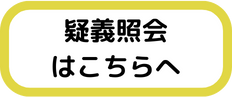鼻うがい
鼻うがいの目的
異物の除去
鼻腔内部には、微細な毛(維毛)があり、これが外部からの異物をキャッチする役割を持っています。しかし、多量のほこりや大気中の汚染物質が堆積すると、この機能が低下する可能性があります。鼻うがいは、これらの余分な異物を除去し、鼻の機能を維持するために役立ちます。
感染予防
鼻は呼吸器系の入り口となる部位であり、ウイルスや細菌の侵入経路ともなりえます。特定の細菌やウイルスが鼻腔内に定着することで、上気道感染症のリスクが上昇します。鼻うがいは、これらの病原体を物理的に洗い流すことで、感染のリスクを低減させることが期待されます。
アレルギー対策
アレルギー反応は、特定のアレルゲンが体内に侵入することで起こります。花粉やダニの排泄物など、鼻を通じて体内に侵入するアレルゲンを洗い流すことで、アレルギー反応の発症や症状の悪化を抑制することが可能です。
どのような方におすすめか?
・風邪予防(コロナ対策):新型コロナウイルスの陽性判定後であっても、1日2回の鼻洗浄によって入院や死亡のリスクが低減することが報告されています。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36007135/
- 花粉症
- 後鼻漏のある方
- 副鼻腔炎になりやすい方
- 慢性上咽頭炎およびBスポット療法中
鼻うがいのやり方
基本的には下記のような専用の器具を使用した方が良いです。
日本にはすでに市販されている鼻うがい容器が幾つもあります。
- 低容量:ハナノアa(30mL)、ハナノアb(50mL)
- 中容量:ナサリン(60mL×2)、ハナクリーンS (150mL)、ハナオート(190mL)
- 高容量:フロー・サイナスケア(200mL)、サイナスリンス(240mL)
- 超高容量:ハナ通り(250mL)、Waterpulse(300mL)、ハナクリーンα(300mL)
個人的には、鼻腔へのフィット感とサイズ感からサイナスリンスが好きです(全部試したわけではないのであくまで感想です)。どの製品でも目的は達成できると思いますが、それぞれの鼻の穴のサイズや鼻腔の形態でやりやすさは変わってくると思います。
専用の洗浄剤が付いているものがほとんどですが、洗浄液は後述するように水道水で生理食塩水を作成すれば良いと思います。
準備
ハナクリーンSの場合

- ボトルキャップをはずし、ボトル側面のHライン(150ml)まで 給湯器で
約40℃のお湯(もしくは熱めのシャワー)をいれます。給湯器を使用しない
場合はCのラインまで水を入れてHのラインまで熱湯を注ぎ足すと約40℃になります。ボトル裏面にある温度計で適温になっていることを確認します。 - 付属の洗浄剤サーレS1包を入れてよく溶かします。(後述の自作洗浄液で代用可能)
- ボトルキャップ上方のノズルを上まで完全に引き上げ、キャップを締めます。
サイナス・リンスの場合

- ボトルに36℃程度のお湯を240ml入れます。(自作の洗浄液でも代用可能)
- 付属の洗浄剤をボトルに入れてよく溶かします。
- キャップを締め、軽く振って洗浄剤を溶かします。
※上記以外の洗浄器を使用される場合には添付の説明書を参照してください。
食塩を使った洗浄液の作り方
鼻に水をいれるとなると、痛いのでは、と不安になる方も多いと思います。子どものころプールで水が入って、鼻がツーンとした思い出がよみがえりますね。
ちゃんと浸透圧を調整し、適切な温度で鼻うがいすれば、痛くありません。それが生理食塩水なのです。
生理食塩水は浸透圧が体の組織に合っているため、しみることがなく、組織へのダメージも少ないと考えられています。
売られているリフィル用の粉などを使用しなくても、簡単に作成することができます。
- 食塩4.5g(小さじ1杯弱 あじしおや他のミネラルを含む岩塩などは使用しないようにしてください)
- 水道水500mL
※水道水で良いのか?
実は、アメリカで鼻うがいをした際に、水の中に含まれていたアメーバのせいでアメーバ脳炎になって死亡したという症例が報告されています。アメリカFDAは、水道水をそのまま鼻洗浄に用いないように、と警告を出しています。 アメーバ脳炎の原因となるのはネグレリア・フォーレリという原虫(寄生虫の一種)です。温暖な気候の淡水に生息していると言われています。
日本で飲用の水道水を用いる限りはアメーバ脳炎のリスクは極めて低いと思います。日本の上水はかなり清潔であり、アメーバが繁殖している可能性は非常に低いです。ただし、余裕がある方は煮沸した水道水やミネラルウォーターを用いていただいた方が良いと思います。
鼻うがいの手順
- 前かがみになり、ノズルを軽く鼻に押しあてます。
- 「えー」と声を出しながらボトル中心部を押して鼻内を洗浄します。数プッシュごとに左右切り替えて両鼻から洗浄を行いましょう。
- 洗浄後は鼻を片方ずつ優しくかんで、鼻に残った洗浄液を出します。
- 洗浄が終わったらボトル1/3まで水を入れ、ボトルを押して中に残った洗浄液を洗い流し、内部の水分が取り除けるまで空押しします。(カビや細菌の繁殖予防に必ず行ってください)
- ノズルをよく洗い、全体も軽く洗ってから水気をふき取り、しっかり自然乾燥してください。
適切な回数は?
1日1~2回程度 片側100~150mlずつ
※鼻の手術を受けた後は一般的に1日3回の洗浄が推奨されます。
たとえば、朝、帰宅後、就寝前に洗浄することをお勧めします。 (あまり洗いすぎるのは、必要な粘膜の粘液まで洗い流してしまうことになりますのでお勧めしません。)
鼻うがいの注意点
洗浄液は①洗浄液を入れた鼻孔から、②反対側の鼻孔から、③鼻の奥を通って口からでてきます。洗浄液がどこからでてきても鼻の中は充分に洗えています。無理に口から出そうとして水圧を強くしすぎたり、反対の鼻を塞いだり、吸い込んだりしないでください。
洗浄後しばらくしてから鼻の奥に残った洗浄液が出てくることがありますが問題はありません。前かがみになり、首を左右に傾けると出やすくなります。耳に負担がかかるため鼻を強くかまないでください。
※鼻の奥には耳とのどをつなぐ管があるので、圧がかかりすぎると中耳炎を起こすことがあります。初回の洗浄時にはゆっくり弱い力で押し、徐々に自分に合った圧力に調整するようにしてください。鼻を密閉しなくても洗浄はできますのでノズルを強く押し付けすぎないように注意してください。耳に痛みを感じた場合には洗浄を中止してください。
やりすぎない
鼻腔は、粘液を分泌して外部の病原体や異物をキャッチする役割があります。頻繁な鼻うがいは、この粘液を過度に洗い流してしまい、自然なバリア機能が低下する恐れがあります。
適切な濃度温度を心がける
塩の量や水の温度を適切に調整することで、鼻腔の粘膜への刺激を最小限に抑えることができます。特に冷たすぎる水や濃すぎる塩水は、粘膜に刺激を与えるため避けるようにしましょう。
鼻の症状がひどすぎる時は注意
急性副鼻腔炎の急性期では、鼻に出ている膿性鼻汁が耳にまわって中耳炎を引き起こしてしまうことがあります。
鼻うがいの最中に唾液や洗浄水を飲み込まない
鼻うがいをする際には生理食塩水を鼻からゆっくりと注入していくのですが、この際に唾液や洗浄水を飲み込んでしまうと、耳管と呼ばれる部分に水が入り、中耳炎を起こすことがあります。また、鼻腔の中に水分が残っている状態で鼻をかんでも、中耳炎の原因となります。
よくある質問
入れても同じ側の鼻から出てきてしまいます
入れた鼻の反対側の鼻や口から出てこなくても大丈夫です。やっているうちにだんだん出来るようになってくることが多いですが、できなくても問題ありません。また、無理に反対側や口から出そうとしてすすったりしないでください。
耳が毎回痛くなります
耳管(耳と鼻をつないでいる管)が開きやすいのかもしれません。中耳炎を発症してしまうリスクがあるので、今よりも優しめにやる、必ず前かがみであまり上を向かないようにする、鼻すすりをしないなどの対応をしてもなお同じ症状であれば、鼻うがいはやらない方が良いと思います。
洗浄後に少し時間が経ってから鼻から液体が出てくることがあります
洗浄時に副鼻腔に残った洗浄液が前かがみになったり、時間を置いて出てくることがあります。
副鼻腔までしっかり洗い流せている証ですのでご安心いただき、再度やさしく鼻をかみなおしてください。
まとめ
鼻うがいは、適切な方法で行うことで多くのメリットを享受することができますが、不適切な方法で行うと、鼻腔の健康を損なう恐れがあります。
正しい知識と技術を持って実施することで、鼻の健康を維持し、さまざまな症状の予防や改善に役立てることができます。