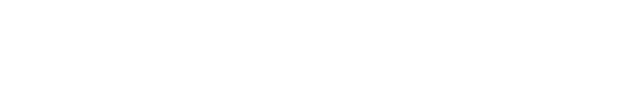寒暖差アレルギー|メカニズム、症状、治療法、予防法
季節の変わり目や、気温の急激な変化によって、鼻水、くしゃみ、鼻づまりなどの症状に悩まされることはありませんか?もしかしたらそれは、「寒暖差アレルギー」かもしれません。このページでは、寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)について、そのメカニズムから治療法、日常生活での予防法まで詳しく解説します。
寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)とは?
寒暖差アレルギーは、医学的には「血管運動性鼻炎」と呼ばれるもので、アレルギー反応ではなく、温度変化によって鼻の粘膜の血管が過剰に反応する状態です。
アレルギーとの違い
花粉やハウスダストなどのアレルゲンが原因ではなく、IgE抗体も関与しません。
自律神経の関与
急激な温度変化によって自律神経のバランスが乱れることが主な原因と考えられています。特に、副交感神経が優位になると、鼻の血管が拡張し、鼻水などの症状が出やすくなります。
7℃以上の温度差
一般的に、1日の気温差が7℃以上になると症状が出やすいとされています。
症状の特徴
主な症状は、透明でサラサラとした鼻水、くしゃみ、鼻づまりで、目の痒みや充血を伴わないのが特徴です。ただし、鼻水が主な症状で、鼻詰まりはそれほどメインではない場合が多いです。
寒暖差アレルギーが起こるメカニズム
寒暖差アレルギーのメカニズムには、自律神経の乱れと鼻の知覚神経の過敏が深く関わっています。
自律神経のバランスの乱れ
- 自律神経は、交感神経と副交感神経の二つから成り立ち、体の様々な機能をコントロールしています。
- 交感神経: 活動時に優位になり、鼻内の血管を収縮させる働きがあります。=鼻が通ります。
- 副交感神経: リラックス時に優位になり、鼻内の血管を拡張させる働きがあります。=鼻が詰まります。
- 急激な温度変化は、自律神経のバランスを乱し、特に副交感神経が過剰に働くことで鼻の血管が拡張し、鼻水などの症状を引き起こします。
-
高齢者、筋肉量の少ない人、30~40代の成人女性に多い傾向があります
鼻の知覚神経の過敏
- 鼻の粘膜には知覚神経が分布しており、温度変化などの刺激を感知します。
- アレルギー性鼻炎の方は、この知覚神経が過敏になっているため、寒暖差アレルギーも起こしやすい傾向があります。
- 寒暖差などの刺激によって、知覚神経が過敏に反応し、くしゃみや鼻水の症状が現れます。
寒暖差アレルギーの症状
- 鼻水: 透明でサラサラした水のような鼻水が特徴です。
- くしゃみ: 発作的に連続してくしゃみが出ることがあります。
- 鼻づまり: 鼻の粘膜の血管が拡張することで、鼻づまりが起こります。
- その他の症状: まれに、頭痛、倦怠感、食欲不振などを伴うことがあります。
- 目の症状: アレルギー性鼻炎とは異なり、目のかゆみや充血は通常伴いません。
-
人によっては、頭痛や倦怠感、肩こり、寒冷蕁麻疹などの症状が現れることもあります
症状が現れやすい場面
- 朝晩の気温差が大きい時
- 暖房の効いた室内から寒い屋外に出た時
- 冷房の効いた部屋から外へ出た時
- 熱い食べ物を食べた時
- お風呂上り
寒暖差アレルギーと間違えやすい病気
寒暖差アレルギーは、風邪やアレルギー性鼻炎と症状が似ているため、自己判断が難しいことがあります。それぞれの特徴を理解し、適切な対処をすることが重要です。
| 症状 |
寒暖差アレルギー (血管運動性鼻炎) |
風邪 | アレルギー性鼻炎 |
|---|---|---|---|
| 鼻水 | 透明でサラサラ | 黄色く粘り気がある、またはドロッとしている | 透明でサラサラ(悪化すると黄色くなる場合も) |
| くしゃみ | 連続して出る場合が多い | あまり長く続かない | 出やすい |
| 鼻づまり | 鼻水に比べると少ない | ある場合とない場合がある | 出やすい |
| 発熱 | なし | ある場合がある | なし |
| 目のかゆみ | ほとんどない | なし | ある |
| その他の症状 | 温度差で一時的に症状が出る | 喉の痛み、咳、全身の倦怠感などを伴うことがある | 目のかゆみ、皮膚のかゆみ、喘息などを伴うことがある |
寒暖差アレルギーの治療法
寒暖差アレルギーの治療は、根本的なものはなく、症状を和らげる対処療法が中心となります。
薬物療法
- 抗ヒスタミン薬: アレルギー性鼻炎に使われる薬ですが、寒暖差アレルギーには効果が限定的です。効くかどうかは個人差もありますので、まず最初に試してみても良いと思います。
- ステロイド点鼻薬: 鼻の炎症を抑え、症状を緩和する効果が期待できます。副作用が少ないため、比較的安全に使用できます。
- 血管収縮薬: 点鼻薬に含まれることがありますが、長期使用は薬剤性鼻炎を引き起こす可能性があるため、漫然とした使用は推奨されません。
- 漢方薬: 小青竜湯などが用いられることがあります。体質改善や自律神経のバランスを整える目的で使用されます。
手術療法
- 下鼻甲介粘膜レーザー焼灼術: 鼻の粘膜をレーザーで焼灼し、症状を緩和します。
- 後鼻神経切断術: 鼻の知覚神経を遮断し、鼻水やくしゃみを抑えます。症状が重い場合に検討されます。
その他
- 抗コリン作用薬: 鼻水を抑える効果がありますが、副作用(眠気、口の渇きなど)があるため、注意が必要です。
寒暖差アレルギーの予防法
上述のように、効果的な薬物が少ないため、日常生活の中で気を付けていく必要があります。
温度差対策
服装の工夫: 脱ぎ着しやすい服装で体温調節をしましょう。
首、手首、足首の保温: マフラー、手袋、靴下などでこれらの部位を温めましょう。
マスクの着用: 冷たい空気が直接鼻に入るのを防ぎます。
室温調整: 屋内外の温度差を小さくするように、空調を適切に使いましょう。
生活習慣の改善
規則正しい生活: 毎日同じ時間に寝起きし、生活リズムを整えましょう。
十分な睡眠: 質の良い睡眠を確保しましょう。
バランスの取れた食事: 体を温める食材(生姜、唐辛子など)を意識して摂りましょう。
適度な運動: 筋肉量を増やし、体温調節機能を高めましょう。ウォーキングやストレッチなどがおすすめです。
ストレス解消: 自分に合った方法でストレスを解消しましょう。
禁煙: タバコの煙は自律神経を乱す要因になります。
その他
加湿: 鼻の粘膜の乾燥を防ぐために加湿器を使用しましょう。
手首の保温: 手首を温めることも有効です。
入浴: 湯船に浸かり体を温めましょう。
刺激物の回避: タバコの煙や排気ガス、香料などの化学物質を避けましょう。
まとめ
血管運動性鼻炎(寒暖差アレルギー)は、アレルギーではなく、温度変化で鼻粘膜の血管が過剰に反応する状態です。7℃以上の気温差で症状が出やすく、主な原因は自律神経の乱れです。症状は、透明でサラサラした鼻水、くしゃみ、鼻づまりが中心です。
治療は対症療法が中心で、ステロイド点鼻薬や漢方薬が用いられます。抗ヒスタミン薬は効果が低いことが多いです。予防には、体温調節が重要で、衣類の調整やマスク着用が有効です。規則正しい生活、十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動も自律神経を整える上で大切です。
記事執筆者
池袋ながとも耳鼻咽喉科
院長 長友孝文
日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会 専門医

医院情報
医院名 池袋ながとも耳鼻咽喉科
所在地 〒170-0012
豊島区上池袋4-29-9 北池テラス4階
電話番号 03-6903-4187
診療科目 耳鼻咽喉科 / 小児耳鼻咽喉科 / アレルギー科