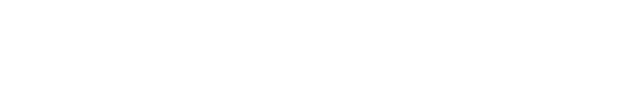〈論文レビュー〉鼻腔内の黄色ブドウ球菌が抑うつ症状に関連?
先日、国際的な学術誌(Nature Microbiology(2025年10月号))に、鼻腔マイクロバイオーム(細菌叢)とうつ病との関連を解明した論文が掲載されました。
これまで、腸内細菌叢が脳機能に影響を与える「腸—脳軸(Gut–Brain Axis)」については広く知られていましたが、本論文は、鼻腔に定着する特定の細菌が、脳内の神経伝達物質に直接影響を与え、うつ病様の行動を促進するメカニズムを明らかにしました。
これは、鼻の治療を行う私たち耳鼻咽喉科医にとって、今後の治療方針に影響を与える可能性を秘めた極めて重要な研究と考えられます。
論文の核心:うつ病患者の鼻に「黄色ブドウ球菌」が著しく多い
この研究では、未治療のうつ病患者100名と健常対照者118名の鼻腔内細菌叢が分析されました。
- 細菌叢の多様性の低下
うつ病患者の鼻腔マイクロバイオームは、健常者と比較して多様性が有意に低いことが示されました。また、細菌叢の構成も両グループ間で有意に異なっていました。 - 黄色ブドウ球菌(S. aureus)の関連
最も多く存在する細菌属・種を分析した結果、健常者と比較してうつ病患者で有意に豊富であったのは、Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)のみでした。
- 重症度との相関
S. aureusの存在量は、うつ病の重症度と有意な正の相関を示しました。また、S. aureusの鼻腔内保菌者(キャリア)の割合も、健常者よりうつ病患者で有意に高かったため、保菌がうつ病のリスク因子となる可能性が示唆されています。
驚くべきメカニズム:鼻腔内の「性ホルモン分解酵素」Hsd12
この研究が最も画期的なのは、S. aureusがうつ病様の行動を誘発する具体的な「鼻—脳軸」のメカニズムを特定した点です。
- 鼻腔内の性ホルモンの減少
うつ病患者の鼻腔内代謝産物(メタボローム)を分析したところ、健常者と比較して、性ホルモンであるエストラジオールとテストステロンのレベルが有意に減少していました。これらの鼻腔内性ホルモンレベルの低下は、うつ病および不安のスコアと有意な負の相関を示しました。
- S. aureusによるホルモン分解
S. aureusは、17B-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼという、これまで知られていなかった酵素を発現しています。このHsd12は、鼻腔内でエストラジオールやテストステロンを分解する働きを持つことが確認されました。
- 脳内神経伝達物質への影響
マウスを用いた実験では、S. aureusの鼻腔内定着により、鼻および脳内の性ホルモンレベルが低下し、その結果、中脳においてドーパミンおよびセロトニンのレベルが減少することが確認されました。ドーパミンやセロトニンは感情制御に重要な役割を果たしており、その低下がうつ様行動を促進する鍵となります。
このメカニズムは、S. aureusが宿主の全身性の炎症を伴うことなく、鼻という局所的な環境で性ホルモンを操作し、脳機能に影響を与えるという、驚くべき「鼻—脳軸」の役割を確立しています。
ここまでで言えること/言えないこと
-
言える
-
鼻腔のS. aureusと抑うつの関連(ヒト)、および因果の可能性(マウス)。
機序としてHsd12による性ホルモン分解→DA/5-HT低下が有力。
-
-
まだ言えない
-
人での介入効果(例:除菌、鼻内ホルモン、プロバイオティクス、Hsd12阻害)が気分を改善するかは不明。
-
鼻腔内S. aureusの保菌スクリーニングや除菌を“うつ”治療に推奨できる段階ではない。
-
個人的な意見と推察:慢性上咽頭炎との関連性
さて、ここからは、私個人の臨床的な考察を述べさせていただきます(これは論文の直接的な結論ではなく、あくまで推測の域を出ません)。
当院で多く行っている慢性上咽頭炎(CNE)に対するEAT(上咽頭擦過療法、Bスポット治療)の患者さんについて考えると、この黄色ブドウ球菌の知見は非常に興味深い関連性を示唆します。
1. 上咽頭は黄色ブドウ球菌の温床か?
慢性上咽頭炎の患者さんの上咽頭(鼻腔の奥、喉の上の部分)の細菌培養を行うと、高頻度で黄色ブドウ球菌が検出されています。
上咽頭は鼻腔と喉頭の間に位置し、感染や炎症が慢性化しやすい場所です。本論文が示した「鼻腔内黄色ブドウ球菌保菌」と「うつ病」の関連を考えたとき、上咽頭で黄色ブドウ球菌が慢性的に多く存在している状態、すなわち慢性上咽頭炎の病態が、この細菌による性ホルモン分解がメカニズムの「作用点」となっている可能性はないでしょうか。
※※)ただし、正常健常人でも黄色ブドウ球菌は良く検出される菌です。上咽頭炎患者で有意に多いかはわかっておりません。
検索しうる範囲では、慢性上咽頭炎患者と上咽頭細菌叢の関係について記された論文はありませんでした。
しかし、高齢者における上咽頭細菌叢の検討をされた論文はあり、それによるとCNS、Corynebacteriumが多く、次いで黄色ブドウ球菌でした。つまり健常人でもそれなりに上咽頭に黄色ブドウ球菌が認められるということです。
それと今回の研究では、スワブを鼻腔粘膜の表面に沿って深さ 2〜3 cm まで挿入したとのことですので、上咽頭までは到達していません。あくまで鼻腔内の話です。
上咽頭炎=黄色ブドウ球菌が多い=除菌すれば改善、とするのは過大解釈と考えております。
2. 慢性上咽頭炎患者の全身症状と精神症状
慢性上咽頭炎の患者さんは、局所の炎症症状(鼻や喉の不快感)だけでなく、頭痛、倦怠感、自律神経失調症様の症状、そして時に抑うつ傾向や不安感といった全身症状や精神神経症状を訴えることが多々あります。
もし、上咽頭に慢性的に存在する黄色ブドウ球菌が、このHsd12酵素 を介して鼻腔・上咽頭の性ホルモンを分解し続け、それが脳内のドーパミンやセロトニンの低下につながっているとすれば、慢性上咽頭炎患者さんが訴えるこれらの精神神経症状の一部を、細菌由来の代謝異常として説明できるかもしれません。
3. EAT治療の意義の再解釈?
EAT治療の作用機序は大きく3つが示されていますが、上咽頭の炎症を抑えることで局所の細菌バランスを改善しようとすることは、結果的にこの「S. aureusによるホルモン分解」を抑制し、間接的に精神症状の改善に寄与している可能性も推察されます。
もちろん、これはまだ推測の段階であり、慢性上咽頭炎における黄色ブドウ球菌の具体的な作用やHsd12酵素の活動を検証する研究が必要です。
しかし、この論文は、鼻の健康が精神の健康と直接結びついていることを科学的に示し、耳鼻咽喉科治療の対象が、単なる「鼻の通り」や「喉の痛み」に留まらない可能性を示唆していると言えるでしょう。
まとめ
今回の研究は、黄色ブドウ球菌保菌が、炎症を伴わずにうつ病のリスク因子となり得ることを示しました。これは、鼻腔のマイクロバイオームの組成(dysbiosis)が、ヒトの生理機能や行動に大きな影響を与える という「鼻—脳軸」の重要性を裏付けるものです。