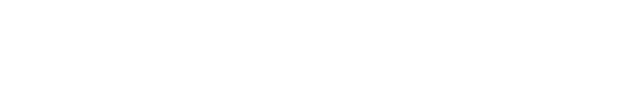喉の痛み: 原因から対処法・予防策まで
喉の痛みとは?
「喉の痛み」とは、咽頭(いんとう)や喉頭(こうとう)など喉の奥の粘膜に炎症や刺激が生じ、ヒリヒリ・イガイガした痛みや不快感を感じる症状です。医学的には喉の奥の炎症を「咽頭炎(いんとうえん、pharyngitis)」と呼び、一般的な風邪症状の一つとしても現れます。
喉の痛みがあると飲み込むときに強く痛んだり、乾燥してイガイガした感じ、また声がかすれることもあります。発熱や咳、鼻水、リンパ節の腫れなど他の症状を伴う場合も多く、症状は通常3~5日程度続くことが多いです。
喉の痛みは非常によくある症状で、人口の約7.5%が任意の3か月間に喉の痛みを経験するという統計もあります。一年に2~3回程度の頻度で喉の痛みを感じる人も珍しくありません。
例えば米国では、喉の痛み(咽頭炎)のために年間約1,500万人もの人が医療機関を受診しています。日本でも冬場の風邪やインフルエンザの流行期には、多くの人が喉の痛みを訴えて病院やクリニックを訪れます。多くの場合、喉の痛み自体は命に関わるものではなく数日~1週間程度で自然に治ることがほとんどです。
しかし原因によっては適切な治療が必要だったり、稀に喉の深部の感染が悪化して重篤化するケースもあります。そこでまずは、喉の痛みの主な原因について詳しく見ていきましょう。
喉の痛みの主な原因
喉が痛くなる原因は大きく分けて 感染症によるもの と 感染症以外(環境や生活習慣・その他疾患)のもの に分類できます。それぞれ、具体的にどのような要因が喉の痛みを引き起こすのか確認してみましょう。
ウイルス・細菌など感染症による喉の痛み
喉の痛みの原因として最も多いのはウイルスや細菌などによる感染症です。実は「のどが痛い」という症状の大部分はウイルス感染によるもので、細菌感染が原因となっているケースは一部に限られます。
日本感染症学会の提言によれば、喉の痛みを主症状とする急性咽頭炎・扁桃炎患者の原因微生物の大部分はウイルスであり、最も重要な原因菌はA群溶血性レンサ球菌(GAS)だとされています。具体的には、小児では喉の痛み全体の約20~30%が溶連菌(ようれんきん、A群β溶血性連鎖球菌)感染によるもので、成人では約5~10%程度が溶連菌性咽頭炎と推計されています。残りはウイルス性が大半で、一部に他の細菌や真菌などが含まれます。
風邪(かぜ症候群)・インフルエンザなどウイルス感染
最も典型的な喉の痛みの原因です。ライノウイルス、コロナウイルス、アデノウイルス、インフルエンザウイルスなど様々なウイルスが咽頭に感染し炎症を起こします。
ウイルス性の咽頭炎では、喉の痛みに加えて発熱、咳、鼻水、くしゃみなど風邪のような症状が伴うことが多いのが特徴です。通常は急に喉がイガイガし始めて、その後1~2日で鼻水や咳が出るという経過をたどります。
ウイルス感染による喉の痛みは自然に改善することが多く、対症療法で様子を見るのが一般的です(治療法は後述)。特にかぜ症候群では、喉の痛みとともに軽い発熱や倦怠感が出ますが、重症化することはまれです。ただしインフルエンザでは高熱と全身倦怠感が強く、喉の痛みもより激しくなる傾向があります。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)でも喉の痛みがよく見られます。こうしたウイルス感染症の場合、喉の痛みはウイルスが喉の粘膜に感染・増殖することで生じる炎症反応によるものです。
扁桃炎(溶連菌など細菌感染)

喉の痛みの原因となる細菌の中で最も重要なのがA群溶血性レンサ球菌(Group A Streptococcus、いわゆる「溶連菌」)です。溶連菌が喉に感染すると溶連菌性咽頭炎を発症します。溶連菌感染は学童期の子どもに多いですが、成人でも喉の細菌感染原因の一部(数%~1割程度)を占めます。溶連菌性の喉の痛みはウイルス性と症状が少し異なり、38℃以上の高熱や強い喉の腫れ・痛みを伴う一方で、咳や鼻水は出ないことが多いのが特徴です。喉を覗くと扁桃(口蓋扁桃)が赤く腫れて膿(白い斑点)が付着していたり、軟口蓋に小さな点状の出血(点状出血)が見られることもあります。首のリンパ節(顎の下あたり)が腫れて押すと痛むことも典型的です。
溶連菌感染症は抗菌薬(抗生物質)による治療が必要で、適切に治療することで症状を早く改善させるだけでなく、リウマチ熱や糸球体腎炎などの重い合併症を予防できます。実際、抗生物質の普及によりリウマチ熱の発症率は激減しました。
溶連菌以外にも、マイコプラズマ肺炎や百日咳など一部の細菌感染で喉が痛くなることがありますが、頻度は高くありません。
上咽頭炎
意外と見逃されがちなのが上咽頭炎です。上咽頭の炎症は、ウイルス、空気の汚れ、アレルギー、喫煙、胃酸逆流など様々な原因で起こります。上咽頭とは「鼻多く」「鼻と喉の間」などと表現される部位にあり、上咽頭の炎症を「のど」の痛みと感じることは結構多いです。のどの痛みを訴える患者の多くは痛みの原因が中咽頭や下咽頭ではなく上咽頭であることも報告されています。上〜下咽頭に分布する舌咽神経から伝わる刺激を脳が誤認しているのかもしれません。
例えば咽頭痛の症状で内科や耳鼻科を受診して、口をあ〜んと診てもらっても、「たいして赤くないですね」と医師に言われることも少なくありません。自分では相当痛いのにたいしたことない??と思ってことはないでしょうか。実は上咽頭に強い炎症があることも少なくありません。上咽頭は通常の診察では見えないため、一見すると軽い炎症に見えてしまうのです。
真菌感染
ごく稀ですが、免疫力が低下している人ではカンジダなど真菌(カビ)による咽頭炎が起こることがあります。ステロイド薬や抗生物質の長期使用で口腔カンジダ症になり、その延長で喉に痛みが出るケースなどです。ただ一般の健常者では真菌性はほとんど心配ありません。
その他の感染症
伝染性単核症(でんせんせいたんかくしょう、いわゆるキス病。EBウイルス感染)も10代~20代の若者を中心に喉の強い痛みと発熱・リンパ節腫脹を起こす病気です。症状が溶連菌感染と似ていますが抗生物質は無効で、自然経過で数週間かけて改善します。
また、性感染症である淋菌(淋病)やクラミジアがオーラルセックスによって咽頭に感染すると喉の痛みを生じる場合があります。特定の原因が疑われる場合には検査が必要です。
小児ではヘルパンギーナ(コクサッキーウイルス感染)や手足口病でも喉に水疱や潰瘍ができ痛みを伴います。RSウイルスやクループ症候群では喉の奥が腫れて「ケンケン」という咳や嗄声(声がれ)を伴うこともあります。いずれにせよ、感染症による喉の痛みの場合は多くが数日~1週間程度で軽快に向かいます。
アレルギーや乾燥、生活習慣などその他の要因
感染症ではない原因でも、喉の痛みや違和感が生じることがあります。以下に主な非感染性の原因を挙げます。
アレルギー
花粉症などのアレルギー性鼻炎のある方は、鼻水が喉に垂れて(後鼻漏)喉の粘膜を刺激し、慢性的な喉のイガイガ・痛みの原因になります。特に春の花粉シーズンなどは「風邪ではないのに喉が痛い」という場合、アレルギー反応による咽頭の炎症が考えられます。対策としてはアレルギー治療薬の内服や点鼻で炎症を抑えることが有効です。
空気の乾燥
冬場など湿度が低い環境では、喉の粘膜が乾燥して防御機能が低下し、痛みや違和感を感じやすくなります。特に睡眠中に口で呼吸する癖がある方は、朝起きたとき喉がカラカラに渇いて痛むことがあります。乾燥した粘膜はウイルスや細菌にも感染されやすくなるため、冬の乾燥シーズンには加湿器の使用やマスク着用で適度な湿度(50~60%程度が理想)を保つことが喉の健康維持に重要です。
喫煙・大気汚染
タバコの煙や大気中の粉塵・汚染物質は喉の粘膜を直接刺激し、慢性的な炎症や痛みを引き起こします。喫煙者が「のどがイガイガする」「痰が絡む」と感じるのは、煙に含まれる有害物質が喉や気道を傷つけているためです。実際、喫煙習慣のある人はない人に比べて慢性的な喉の痛みや咳を訴える割合が高くなります。また受動喫煙も影響するため、家庭内に喫煙者がいる場合は注意が必要です。喉の痛みを改善するには禁煙が何より有効です。工場地帯の大気汚染やホコリっぽい職場環境も同様に喉への刺激となるため、防塵マスクの着用や作業環境の改善が望まれます。
声の酷使(声帯の炎症)
大声での会話や長時間の歌唱(カラオケ)、声を張り上げるような発声を続けると、喉(正確には声帯)の粘膜に機械的刺激が加わり声帯炎や喉頭炎を起こします。これにより喉の痛みや声枯れが生じます。例えばスポーツ観戦で声を出し過ぎた翌日に喉がヒリヒリする、といった経験は多くの方があるでしょう。通常は数日声を安静にしていれば回復しますが、無理に使い続けると慢性化したりポリープができることもあります。「喉を酷使したな」と感じたら、早めに休養を取って喉を労わることが大切です。
胃食道逆流症(GERD)
胃酸が食道を逆流して喉元まで達すると、強い酸性の胃液が咽頭の粘膜を焼いて炎症を起こし、喉のヒリヒリ感や痛みの原因となります。逆流性食道炎のある人が「胸やけとともに喉が焼けるように痛む」と訴えるのはこのためです。特に食後すぐ横になる習慣がある場合や、肥満・妊娠などで腹圧が高まっている場合に起こりやすいです。胃酸逆流が疑われるケースでは、食後すぐ横にならない、寝る時に上半身を少し高くする、胃酸を抑える薬の内服などで対処できます。嘔吐をした後もしばしば喉が荒れて痛みますが、これも吐しゃ物に含まれる胃酸による刺激が原因です。
悪性腫瘍(がん)
稀ではありますが、咽頭癌や喉頭癌といった喉の部位にできる悪性腫瘍でも、初期症状として喉の違和感や軽い痛みが現れることがあります。特徴的なのは、「長期間(2週間以上)痛みや違和感が治まらない」「片側の喉だけが痛む」「耳の痛みを伴う」「血痰が出る」などの場合です。リスク因子として喫煙・多量飲酒の習慣がある中高年の方で、上述のような症状が続く場合は耳鼻咽喉科で詳細な検査を受けることが勧められます。ただし、喉のがんは痛みよりもしこり(首のリンパ節転移による腫れ)や声のかすれで気付かれるケースが多く、痛みだけでいきなり疑う必要は過度に心配しなくて大丈夫です。
以上が主な原因の一覧です。ご自身の喉の痛みの原因に心当たりはありましたでしょうか? 次の章では、「では実際に喉が痛くなったとき、どのように対処すれば良いのか」を、医学的な根拠を示しながら具体的に説明します。
喉が痛いときの対処法・治療法
喉に痛みを感じたとき、症状を和らげ早く治すために取るべき対処法を紹介します。軽い喉の痛みであれば自宅でのセルフケアで改善する場合がほとんどですが、細菌感染などが疑われる場合は医療機関での治療が必要になります。それぞれの状況に応じた対処法を理解しておきましょう。
自宅でできるセルフケア
多くの喉の痛みはウイルス性の風邪などによるため、以下のようなセルフケアで症状の緩和を図りつつ自然治癒を待つのが基本となります。
十分な休養と睡眠
体がウイルスと戦うためには休息が一番です。無理に仕事や学校に行かず、まずはしっかり睡眠をとりましょう。特に声を出すと喉に負担がかかるので、声帯を休ませる(静かに過ごす)ことも大切です。体力の回復とともに免疫力が高まり、治りも早くなります。
水分を十分にとる
喉の粘膜を潤すことで痛みが和らぎ、防御機能も高まります。温かいお茶やスープ、はちみつ入りの白湯などは喉を優しく潤し、痛みを和らげてくれます。反対にカフェインやアルコールは利尿作用で脱水を招き粘膜を乾燥させるため控えましょう。米国で有名なMayo Clinicも「水分を十分に摂り喉を乾燥させないこと」を喉の痛み緩和策として推奨しています。特に発熱で汗をかいているときは意識して多めの水分補給を心がけてください。
うがい(ガラガラうがい)をする
ぬるま湯に食塩を少し溶かした食塩水でのどをうがいすると、喉の痛みや腫れを和らげる効果があります。食塩水が粘膜の浮腫をとり、粘液の分泌を促して潤いを保つためと考えられています。実際、Mayo Clinicは「コップ1杯のぬるま湯に小さじ1/4~1/2の食塩を溶かしたうがい液で喉を洗浄すると、痛みの緩和に役立つ」と具体的に推奨しています。子どもの場合はうがいを飲み込んでしまう恐れがあるため、だいたい6歳以上になって正しく吐き出せるようになってから行いましょう。なお、「イソジン」などヨウ素系のうがい薬については、日本では昔から風邪予防に使われてきましたが、必ずしも有効とは限りません。
京都大学の研究チームが行った無作為化試験では、水うがいを習慣にした群は何もしない群に比べて風邪発症率が40%低下した一方、ヨウ素液でのうがい群では有意な効果が認められませんでした。むしろヨウ素で常在菌まで殺菌することでウイルス侵入を許しやすくした可能性も指摘されています。したがって、日常的な予防には水によるうがいで十分といえます。喉が痛いときも、食後や外出後にこまめにうがいをして喉の粘膜を清潔に保つと炎症が落ち着きやすくなります。
加湿と保温
前述の通り乾燥は喉の大敵です。室内では加湿器を使って湿度を適切に保ちましょう(50~60%程度が目安)。加湿器がない場合も、濡れタオルを部屋に干したり、コップに水を入れて置くだけでも多少の効果があります。就寝時に喉が渇く人はマスクを着用して眠るのも有効です。マスクで自分の吐く息が加湿され喉の潤いが保たれます。また首元を温かくして血行を良くすると粘膜の防御機能が高まるため、冬場はマフラーやネックウォーマーで喉を冷やさないようにするのも良いでしょう。
喉に優しい食べ物・飲み物
喉が痛いときは刺激物や硬い食べ物は避け、喉越しの良いものを摂りましょう。例えばはちみつ入りのホットレモンは、はちみつの殺菌・抗炎症作用とレモンのビタミンC補給で一石二鳥です(※ただし1歳未満の乳児には蜂蜜は厳禁です)。
他にも生姜湯や喉に良いハーブティー(カモミール等)は古くから民間療法的に親しまれています。冷たいアイスクリームやゼリーは痛む喉を麻痺させて一時的に楽にする効果もあります。食事は無理に固形物を摂らず、栄養はおかゆやスープなどで補給すると良いでしょう。
のど飴やトローチ
市販ののど飴や医薬品のトローチには、メントールやハーブ成分が含まれており口腔内の潤いを保ち痛みを和らげます。また飴をなめることで唾液の分泌が促されるのも喉に良い効果です。抗炎症成分や殺菌成分入りのトローチもあります。
その他の民間療法
温かい塩湯で足湯をする、生姜湿布を喉に貼る、ネギを巻く…など様々な民間療法がありますが、医学的エビデンスは十分ではありません。ただ「体を温めリラックスする」といった効果で間接的に症状緩和につながる場合もあります。害のない範囲であれば試してみるのも良いでしょう。ただし、のどスプレー(局所麻酔薬含有)について英国NHSは「単独での効果にはエビデンスが乏しい」としています。刺激の強いスプレーの乱用はかえって喉を傷める可能性もあるため注意が必要です。
病院で受ける治療(薬物療法など)
迅速抗原検査・咽頭培養検査
溶連菌など特定の細菌感染が疑われる場合、綿棒で喉の粘膜をぬぐって検査を行います。迅速抗原検査は数分で結果が出て溶連菌の有無を判定できます。陽性なら細菌感染確定、陰性でも必要に応じ培養検査に回すことがあります。溶連菌以外にもアデノウイルスやインフルエンザウイルスの迅速検査が行われることもあります。明らかなウイルス症状(咳・鼻水など)がある場合は検査せず経過を見ることもガイドラインで推奨されています。
抗生物質(抗菌薬)の投与
溶連菌咽頭炎と診断された場合や、細菌性の扁桃炎などが疑われる場合には抗生物質による治療を行います。第一選択はペニシリン系(アモキシシリンなど)で、通常7~10日間程度の内服が推奨されます。抗生物質は指示された期間きちんと飲み切ることが重要です。途中で症状が良くなっても自己判断で中止すると、菌が十分に死滅せず再燃したり耐性菌の出現を招く恐れがあります。特に小児では、溶連菌感染で抗生剤を途中中断するとリウマチ熱や糸球体腎炎などの合併症リスクが高まります。
なお、ウイルス性の喉の痛みに抗生物質は無効であり、不要な使用は耐性菌を生むだけなので避けます。近年、抗生剤の不適切な処方削減が世界的課題となっており、日本でも「ウイルス性咽頭炎には抗生剤を出さない」ことが医師向け手引きに明記されています。
鎮痛薬・解熱薬の処方
症状が強い場合、医療機関でより効果の高い鎮痛解熱剤(処方用のNSAIDsなど)が処方されることもあります。座薬など剤形の工夫で内服困難時にも対応します。痛みを和らげることで食事や睡眠をとりやすくし、回復を助ける目的です。
ステロイドの使用
症状が著しく、喉の腫れで呼吸や嚥下に支障が出ているような重症例では、一時的にステロイドの内服・点滴を行い炎症と腫れを急速に鎮めることがあります。特に急性喉頭蓋炎や重度の扁桃周囲膿瘍で気道確保が危ぶまれる際には、入院の上ステロイド投与と必要なら外科的処置がとられます。
外科的処置(切開排膿など)
扁桃周囲膿瘍(扁桃の周囲に膿が溜まる合併症)になると、のどの一側が腫れて激痛が走り、口が開けにくくなります。この場合、耳鼻咽喉科医による膿の排出(切開して膿を出す処置)が必要です。局所麻酔下で切開し膿を出すと痛みは劇的に軽減します。また急性喉頭蓋炎では気道確保のため緊急の気管挿管や気管切開が行われることもあります。これらは非常に稀なケースですが、「唾液が飲み込めない」「呼吸が苦しい」といった重篤な症状を認めた場合にはすぐに救急対応が取られます。通常は、このレベルの疾患の場合、病院に行かずに自宅で経過観察するということは困難なほどの症状ですので、放置されてしまうケースはほとんどありません。
基礎疾患への対処
アレルギーが原因であれば抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻でアレルギー治療を行います。胃酸逆流が原因なら胃酸分泌抑制薬(PPIなど)や生活指導が行われます。声帯ポリープが見つかれば音声治療や外科的切除が検討されます。このように喉の痛みの背景にある病気に応じた専門的治療が提供されます。
以上のように、医療機関では原因と重症度に応じて適切な処置がなされます。特に「細菌性かウイルス性か」の鑑別が重要で、必要な場合のみ抗生物質を使うのが現在のスタンダードです。実際、イギリスのNHSも「通常、喉の痛みに抗生物質は不要で、細菌感染が疑われる場合のみ処方される」と案内しています。抗生剤の不用意な乱用は副作用や耐性菌リスクというデメリットがありますが、溶連菌のように使うメリットが明確な場合は速やかに使うことが大切です。メリット・デメリットを医師と相談しながら治療方針を決めると良いでしょう。
喉の痛みを予防するには
喉の痛みを未然に防ぐ、あるいは再発を減らすために、日頃からできる予防策をまとめます。基本は「感染しない・粘膜を守る」ことです。
手洗い・咳エチケットの徹底
風邪やインフルエンザなどウイルス感染を防ぐには、まず手についたウイルスを体内に入れないことが重要です。外出先から帰ったら石鹸を使った手洗いをしっかり行いましょう。手洗いは呼吸器感染症のリスクを大きく減らすことが各種研究で示されています(あるレビューでは適切な手洗いで呼吸器感染の発症リスクがおよそ20~40%低減したとの報告もあります)。また咳やくしゃみが出るときはマスクの着用や袖で口元を覆う咳エチケットを守り、自分の飛沫で他人にうつしたり他人の飛沫を吸い込んだりしないようにします。特に冬場や流行期には人混みを避け、やむを得ず人混みに行くときはマスクを活用してください。
規則正しい生活で免疫力維持
疲労や睡眠不足、栄養不良は免疫機能を低下させ、感染症にかかりやすくなります。バランスの取れた食事(特にビタミンA・C・E、亜鉛など粘膜免疫に関与する栄養素)、十分な睡眠、適度な運動を心がけ、日頃から喉を含む粘膜の抵抗力を高めておきましょう。また空気の乾燥する冬場は前述のように加湿を忘れずに。就寝中のエアコン暖房は乾燥しやすいため弱めに設定するか加湿器との併用が望ましいです。寝る前にコップ一杯の水を飲んでおくのも簡単にできる乾燥対策です。
喫煙者は禁煙を検討
繰り返しになりますが、喉の健康のためには禁煙が最も効果的な予防策の一つです。タバコをやめるだけで慢性的な喉の痛みや咳が改善したという報告も多く、長期的に見れば咽頭癌などのリスク低減にもつながります。家族のためにも禁煙をぜひ検討してください。
マスクの活用
日本では習慣となっていますが、マスク着用は乾燥と感染予防の両面で有効です。冬場に外出する際は喉の保湿のためにもマスクをする、喉が弱い人は就寝時もマスクで保湿する、といった工夫ができます。また急に声を出す必要がある環境(コンサートや応援など)の前にもマスクで喉を温めておくと良いでしょう。
適度な湿度と清潔な環境
部屋の湿度が低すぎないよう注意するとともに、室内のホコリやダニを掃除で減らし、クリーンな空気環境を保つことも喉への刺激を減らします。空気清浄機の使用も有効です。暖房器具による一酸化炭素中毒などは論外ですが、ガスヒーター使用時は換気も忘れずに行いましょう。