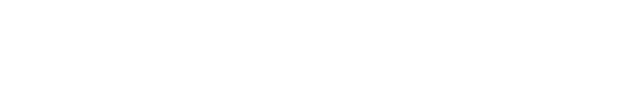鼻水が透明でネバネバするのはなぜ?考えられる原因と正しい対処法
大人になってから「鼻水が透明だけどネバネバして気持ち悪い…」と感じた経験はありませんか?さらさらの水っぽい鼻水とは違い、ティッシュで拭ってもベタつく鼻水が続くと不快ですし、「何か病気では?」と不安になる方もいるでしょう。本記事では耳鼻咽喉科専門医の視点から、透明で粘り気のある鼻水に焦点を当て、その原因と対処法を解説します。
透明でネバネバした鼻水とは?水っぽい鼻水との違い
鼻水は健康な人でも1日に約1~1.5リットル分泌されており、鼻粘膜を潤し吸い込む空気に湿り気を与える大切な役割を担っています。通常の鼻水は無色透明でさらさらしていますが、体調によって粘度や色が変化します。透明でネバネバした鼻水は、さらさらの水様性鼻水に比べて粘液成分(ムチン)が増え、水分が減った状態です。これは鼻粘膜の炎症や乾燥によって引き起こされます。
たとえば風邪(急性鼻炎)の初期には、ウイルスや細菌を排出しようと鼻水が大量に出てサラサラしています。しかし炎症が進むと粘り気のある性状に変わります。一方でアレルギー性鼻炎(花粉症やハウスダストなど)は、発作的なくしゃみ・鼻水が特徴ですが、発作時以外の慢性的な鼻炎状態では透明でネバっとした鼻水が溜まりやすくなります。
黄色や緑色の鼻水との違いにも触れておきましょう。鼻水に黄緑の色がつくのは、白血球(好中球)が感染と戦った死骸や酵素が混ざるためです。副鼻腔炎では膿を含む黄色~緑色のドロっとした鼻水が出ることがあります。
ただし「鼻水が黄色い=必ずしも細菌感染」とは限りません。ウイルス性の鼻風邪でも症状のピークを過ぎる頃には似たような黄色がかった鼻水になることがあります。
色よりも経過日数が重要で、感冒症状が10日以上長引く場合は細菌性副鼻腔炎への移行を疑います。透明か色付きかに関わらず、2週間近く鼻水が続くようなら早めに耳鼻科を受診しましょう(受診の目安は後述)。
まとめると、透明でネバネバした鼻水は「炎症はあるが膿(細菌感染)は強くない状態」を反映していることが多いです。以下では具体的な原因ごとの特徴を見ていきましょう。
透明でネバネバした鼻水の原因と症状の見分け方
透明で粘度の高い鼻水を引き起こす代表的な原因には、アレルギー性鼻炎, 副鼻腔炎(慢性副鼻腔炎・好酸球性副鼻腔炎)、そして鼻粘膜の乾燥などの環境要因があります。それぞれ症状の出方に特徴がありますので、自分の鼻水がどの原因に近いかチェックしてみましょう。
アレルギー性鼻炎(花粉症・通年性アレルギー)
アレルギー性鼻炎は、花粉やハウスダストなどの抗原(アレルゲン)に対して免疫反応が過剰に起こり、鼻粘膜に慢性的な炎症が生じる病気です。典型的な症状の三徴は「くしゃみ・水っぽい鼻水・鼻づまり」で、目のかゆみや涙目、喉の違和感を伴うこともあります。
鼻水は基本的に無色透明でさらさらしています。スギ花粉症など季節性アレルギーでは、大量の水様鼻汁が短期間に出ます。一方、ダニやホコリによる通年性アレルギー性鼻炎では、一年中じわじわと粘り気のある鼻水が出て鼻づまりが続く場合があります。発作的なくしゃみの後にティッシュが手放せなくなるほど出る鼻水はサラサラしていますが、その時々の症状が落ち着いた間歇期には粘度の高い鼻汁が残留しがちです。朝起きた直後やほこりっぽい環境で鼻をすすったときに、透明でネバっとした鼻汁が喉に落ちる(後鼻漏)感じがする場合、アレルギー性鼻炎が疑われます。
日本ではアレルギー性鼻炎の患者数が年々増加しています。ある全国疫学調査では日本人の約49%が何らかのアレルギー性鼻炎に罹患しているとの報告もあり、花粉症だけでも国民の3~4割に達する“国民病”です。もし毎年決まった季節に症状がひどくなる場合は花粉症の可能性が高く、季節に関係なく一年中症状があるならダニ・ハウスダストなど通年性アレルギーが疑われます。
急性鼻炎・かぜ(ウイルス性鼻炎)
透明なネバネバ鼻水の原因として見逃せないのが、風邪(急性上気道炎)です。
いわゆる鼻かぜでは、ウイルス感染により鼻粘膜に急性の炎症が起こります。初期はさらさらとした大量の水様鼻水が出ますが、数日経つと粘度が増してきます。これは、ウイルスと戦う免疫反応で粘液の分泌が活発になり、白血球や抗体を含む粘っこい鼻水に性状が変化するためです。
風邪による鼻水は通常1週間程度で自然に治まります。しかし、ウイルス撃退後も鼻水や鼻づまりが長引くときは細菌の二次感染により副鼻腔炎を併発している可能性があります。黄色や黄緑色の膿性鼻汁に変わり、発熱や顔面の痛みが出てきたら要注意です。特に感冒症状が10日以上続く場合は、細菌性副鼻腔炎(蓄膿症)への移行が疑われるため、耳鼻科受診を検討してください。
なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)でも初期に透明~白色の粘い鼻水が出ることがありますが、発熱・嗅覚異常・全身倦怠感など他の症状を伴う点で風邪や花粉症と異なります。
いずれにせよ、「ただの風邪」と思っていた鼻水が2週間以上治らない場合は医療機関で評価を受けるのが安全です。
慢性副鼻腔炎(蓄膿症)
慢性副鼻腔炎(ちくのう症)は、鼻腔とつながった副鼻腔という空洞に炎症が持続する病気です。通常、かぜ等で起こる急性副鼻腔炎が何度も繰り返されたり長引いたりすることで慢性化します。
症状の三大兆候は、(1) 鼻づまり、(2) 粘り気の強い鼻水(膿性鼻汁)、(3) 嗅覚低下です。鼻水は黄色~黄白色のこともありますが、感染の程度によっては透明なネバネバ鼻水がだらだら続くだけの場合もあります。
とくに慢性期には膿の量が多くないため、透明~白濁した粘液性の鼻汁が常に喉に落ちる(後鼻漏)のが典型です。
慢性副鼻腔炎の人は慢性的な鼻づまりにも悩まされます。両側の鼻が詰まり、マスクをしていなくても口呼吸になりがちです。また、副鼻腔に膿や粘液がたまるため、頬や目の奥、額に重苦しい圧迫感や頭重感が生じます。ひどい時は顔面痛や歯痛を感じることもあります。匂いを感じる嗅覚細胞にも炎症が及ぶため、においがわからない・味がしないといった嗅覚障害を伴うことも少なくありません。
副鼻腔炎が慢性化すると完治までに時間がかかります。日本では慢性副鼻腔炎の患者数は約100万~200万人に上ると推定されます。放置すればポリープ(鼻茸)が鼻腔内に発生し、さらに鼻づまり・嗅覚低下が悪化します。
実際、慢性副鼻腔炎患者の約半数に鼻茸の合併がみられるとの報告もあります。鼻茸が大きくなると鼻腔をふさいでしまい、鼻水がうまく排出されず後鼻漏が強まります。
もし「長引くネバネバ鼻水」と「鼻づまり・嗅覚低下」がセットで当てはまるなら、慢性副鼻腔炎の疑いが高いです。
副鼻腔炎は鼻内視鏡検査やCT検査をしないと詳しい診断ができません。早めに耳鼻咽喉科を受診して適切な治療を受けることをおすすめします。
好酸球性副鼻腔炎(難治性副鼻腔炎)
好酸球性副鼻腔炎は、慢性副鼻腔炎の中でも特に難治性とされるタイプの副鼻腔炎です。両方の鼻腔に鼻茸がびっしりと発生し、内視鏡下手術で取り除いても短期間で再発してしまうのが特徴です。病理検査で鼻茸中に多数の好酸球という白血球が認められるためこの名があります。
好酸球性副鼻腔炎の症状自体は、慢性副鼻腔炎とほぼ同様に鼻づまり・粘性鼻汁・嗅覚障害が主体です。ただし以下の点で通常の副鼻腔炎と異なります。
-
気管支喘息の合併率が高い(約半数の患者に喘息あり)。鼻と気管支のアレルギー炎症がリンクしており、発作的な咳込みや喘鳴を伴うことがある。
-
アスピリン不耐症を合併することがある。鎮痛薬のアスピリンやNSAIDsで喘息発作やショックを起こすタイプの喘息(NSAIDs過敏喘息)患者に好酸球性副鼻腔炎が多いとされる。
-
ステロイド治療に反応しやすい。内服の副腎皮質ステロイドで鼻茸が劇的に縮小し症状が軽快する。ただしステロイドをやめると再燃しやすい。
-
好酸球性副鼻腔炎そのものは命に関わる病気ではないですが、完治が難しく厚生労働省から指定難病(管理番号306)に認定されています。2015年に指定難病となり、患者数は近年増加傾向です(日本で中等症以上の患者が約2万人と推計)。
好酸球性副鼻腔炎が疑われるのは、鼻茸が両側に多発し、なおかつ嗅覚消失や喘息の併発があるケースです。
治療には副鼻腔手術に加えてステロイド内服を反復する必要があります。最近では生物学的製剤(デュピルマブ等)が登場し、難治例に対して有望な結果を示しています。
環境要因・乾燥・その他の原因
明らかな鼻炎や副鼻腔炎がなくても、環境要因や生活習慣によって鼻水がネバネバになることがあります。
代表的なのは空気の乾燥です。湿度が低い環境では鼻粘膜からの水分が蒸発しやすく、粘液が濃縮されてしまいます。その結果、通常はさらさら流れる鼻水がねっとりと粘稠な状態になり、鼻をかんでも出し切れず喉に張り付く感じがします。冬場に暖房を長時間つけている部屋や、湿度が30%以下に下がる環境では特に注意が必要です。
実際、「乾燥した環境や加齢により鼻腔内の粘膜分泌が減少することで鼻水が粘る」ことは臨床的にも指摘されています。ご高齢の方や長時間空調の効いた室内で過ごす方では、鼻の中がカラカラに乾燥しているケースもあります。乾燥による鼻粘膜のダメージは、粘膜の防御機能低下や血管の脆弱化を招き、鼻出血の原因にもなります。鼻水に血が混じるほど乾燥が進んでいる場合は、加湿や保湿ケアが急務です。
また、薬剤性鼻炎も透明な慢性鼻汁の原因となります。市販の点鼻薬(血管収縮剤入り)を長期間連用すると、薬が切れたときにかえって強い鼻づまりと粘液分泌が起こることがあります(いわゆるリバウンド現象)。これは薬剤による鼻粘膜の慢性炎症で、治療には点鼻薬の中止とステロイド点鼻などが必要になります。
その他、自律神経の乱れによる血管運動性鼻炎(温度差や強い匂いで発作的に鼻水が出る)や、妊娠中のホルモン変化による妊娠性鼻炎でも、透明な鼻水が続くことがあります。
このように環境や体質による生理的な鼻水もありますが、「透明だから安心」とは限りません。
粘り気のある鼻水を改善するセルフケア方法
透明でネバネバした鼻水が出るとき、症状が軽度であればセルフケアである程度対処できます。
生理食塩水で鼻うがいをする
鼻うがい(鼻洗浄)は、食塩水で鼻の中を洗い流すセルフケアです。鼻腔内に残った粘性の鼻水やアレルギー物質(花粉・ハウスダスト)を物理的に除去できるため、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎の症状緩和に有効とされています。
実際、アレルギー性鼻炎の患者を対象にした複数の臨床研究でも、鼻洗浄により鼻づまり・鼻水・くしゃみの症状が改善したとの報告があります。2018年のコクランレビュー(国際的なエビデンス評価)でも「生理食塩水による鼻洗浄は、ステロイドや抗ヒスタミン薬に匹敵する安全で安価な補助療法」と結論づけられています。
鼻うがいのやり方は次の通りです。
-
ぬるま湯で作った生理食塩水(0.9%食塩水)を用意する。市販の鼻洗浄キットや、食塩水入りのボトル製剤(鼻うがい専用液)を使うと手軽です。
-
顔を前に少し傾けて片方の鼻孔にノズルを当て、口で息をしながら食塩水を鼻の中に注入します。
-
食塩水を鼻腔内に通過させ、反対側の鼻孔または口から出すイメージで流します(途中で飲み込んでも問題ありません)。
-
洗浄後は顔を下向きにして静かに鼻をかみ、残った液や鼻汁を出します。
正しく行えば鼻うがいは痛くありません。むしろ洗浄後は鼻腔がスッキリして爽快感があります。「鼻うがいは初めてで怖い」という方は、ぬるま湯に食塩を溶かした洗浄液をコップに用意し、片鼻ずつゆっくり吸い込んで吐き出す方法から試しても良いでしょう。鼻腔内にこびりついた粘調な鼻水を物理的に排出できるため、後鼻漏が軽減して喉のイガイガ感が和らいだり、鼻づまりが一時的に改善したりする効果が期待できます。
花粉症シーズンや風邪の流行期には予防目的で1日1~2回行っても構いません。ただし、やりすぎは必要な粘液まで洗い流してしまう可能性があるため注意しましょう。基本的には朝晩1日2回程度に留め、鼻粘膜に違和感や痛みを感じたら頻度を減らしてください。
加湿と水分補給で鼻粘膜の乾燥を防ぐ
乾燥対策はネバネバ鼻水を改善・予防する上で非常に重要です。鼻水が粘る根本要因の一つは粘膜の乾燥による水分減少だからです。そこで、以下のポイントに留意して生活環境を整えましょう。
-
室内の湿度を40~60%程度に保つ。乾燥は鼻粘膜への刺激となり鼻水を過剰に分泌させるため、加湿器などで適度な湿度を維持するのが望ましいです。湿度40~60%は人が快適に感じるだけでなく、粘膜繊毛の動きが正常に働く環境でもあります。加湿器がない場合は、濡れタオルや洗濯物を室内に干したり、観葉植物を置いたりしても多少の加湿効果があります。就寝時は寝室に加湿器を設置し、鼻と喉の乾燥予防に努めましょう。
-
こまめな水分補給をする。体の水分が不足すると、当然ながら鼻粘膜も乾きやすくなります。粘膜が乾燥すると粘液が濃縮され、ますます鼻水がネバつく悪循環に陥ります。特に汗をかきにくい冬場でも、知らず知らず水分不足になりがちです。意識して1日1.5~2リットル程度の水分を摂りましょう。朝起きた時や運動後など、喉が渇いていなくても定期的に水を飲む習慣が効果的です。
「温かいお茶やスープを飲んで体を温める」「食事で汁物や水分の多い果物を摂る」ことも粘膜の潤い維持に有用です。十分な水分補給は風邪予防や全身の健康管理にもつながります。 -
鼻腔内を保湿・保護する。乾燥がひどいときは、ワセリンを綿棒で鼻の穴の入口に塗ると保湿バリアになります。ドラッグストアで買える生理食塩水スプレーや鼻腔用保湿ジェルも、鼻の中の潤いを保つのに役立ちます。特に高齢者の方は鼻前庭部(鼻の穴周辺)の皮膚が乾いてひび割れし、そこから出血することもあるため、軟膏などでの保護がおすすめです。
-
生活習慣を整える。睡眠不足やストレスは自律神経のバランスを乱し、鼻粘膜の血流や分泌をコントロールする副交感神経の働きにも影響します。
規則正しい生活と十分な睡眠(1日7時間前後)を心がけ、免疫力を維持しましょう。
また、喫煙は厳禁です。タバコの煙は鼻や喉の粘膜を直接刺激し炎症を悪化させるだけでなく、繊毛運動を阻害して粘液の排出を妨げます。鼻水が粘って困っている方は、この機会に禁煙・減煙を強く検討してください。
以上のセルフケアに加え、マスクの着用も鼻粘膜の保護に有効です。特に冬や花粉飛散時期はマスクで外気の冷たさや乾燥を和らげ、鼻腔内に湿度を与える効果があります。マスク内側に湿らせたガーゼを挟むと保湿効果がさらに高まると環境省も推奨しています。
セルフケアによって「朝起きたときのネバつきがマシになった」「後鼻漏による喉の不快感が減った」などの改善がみられればしめたものです。これらの対策は継続が大切なので、症状が落ち着いた後も予防的に続けてみてください。
一方で、十分な対策を講じてもなお鼻水が粘っこく不快な状態が続く場合は、次に述べるように医療機関での治療を検討しましょう。
医師に相談すべき目安と耳鼻科での診察・治療
鼻水が長引くとき、受診を検討すべきサイン
-
鼻水が10日~2週間以上続いている。 透明か色付きかを問わず、鼻水・鼻づまりなど風邪症状が約2週間以上良くならない場合は異常です。副鼻腔炎へ移行している可能性が高いため耳鼻咽喉科で診てもらいましょう。
-
鼻水の粘りがどんどん強くなっている。 はじめは水っぽかったのに日を追うごとにドロッと粘ってきた場合、炎症が悪化しているサインです。自己判断せず専門的な治療が必要です。
-
顔や額が重苦しく痛い。 副鼻腔に膿がたまると頬や額に圧迫感・鈍痛が生じます。特に前屈みになったとき額がズキズキする場合は副鼻腔炎が疑われます。
-
臭いがわからない、味がしない。 鼻づまりがひどく嗅覚が低下している状態です。慢性副鼻腔炎や好酸球性副鼻腔炎でよくみられる症状なので放置しないでください。
-
片方の鼻だけ詰まる・鼻水が出る。 慢性鼻炎・副鼻腔炎は通常両側性ですが、片側だけの鼻閉・鼻漏が続く場合は要注意です。鼻の中のポリープが片側に大きくできているか、まれに鼻腔腫瘍(鼻腔がん、副鼻腔がん)の可能性もあります。少量の鼻血が頻回に混じる場合も含め、早急に耳鼻科受診を検討してください。
-
ゼーゼー息苦しい・咳が長引く。 アレルギー性鼻炎に加え喘息を発症しているか、副鼻腔炎の膿が喉に流れて気管支炎を起こしている恐れがあります。
耳鼻咽喉科で行う診察・検査
耳鼻科を受診すると、まず医師による問診があります。鼻水の状態(色や粘度)、出始めた状況、他の症状の有無(くしゃみ・発熱・頭痛・嗅覚障害・咳など)、これまでの経過や既往症を詳しく尋ねられます。
次に診察として、耳鼻科ならではの器具で鼻の中を観察します。鼻鏡という器具や明るいライトで両鼻腔を覗き、粘膜の腫れ具合や鼻水の出どころ、鼻中隔の曲がり(鼻中隔弯曲症)や鼻茸の有無などを確認します。
必要に応じて細く柔らかいファイバースコープ(内視鏡)を鼻腔内に挿入し、奥まで詳細に観察します。痛みはほとんどありませんが、苦手な方には麻酔薬のスプレーを使ってから行います。
内視鏡では副鼻腔の中を観察することはできませんが副鼻腔の入り口近くを確認することができます。副鼻腔炎の場合、鼻腔内に膿性の鼻汁が流れ出ていることが多いため、内視鏡でも診断が可能なケースが多いです。内視鏡検査は手軽であり、挿入時の痛みや違和感以外のデメリットがないため、被曝の危険性があるレントゲンやCTよりも重宝されるケースが多いです。
続いて、副鼻腔炎が疑われる場合はレントゲン撮影やCT検査で副鼻腔の状態を調べることがあります。副鼻腔が黒く抜けていれば空気が通っていますが、炎症で膿や粘液が溜まっていると白く写って判断材料になります。アレルギー性鼻炎が疑われる場合は、鼻水を少量採取して鼻汁好酸球検査を行うことがあります。顕微鏡で見て好酸球という白血球が多数あればアレルギーの関与が強いとわかります。
さらに具体的なアレルゲンを特定する検査として、血液中のIgE抗体検査を行うこともあります。スギ花粉やダニなど代表的なアレルゲンに対するIgE値を測定し、何に対してアレルギーがあるかを突き止めます。アレルギーがないか調べる目的で、必要に応じて血液検査(好酸球数や総IgE値の測定)も実施されます。
嗅覚障害を訴える場合は、嗅覚検査も行います。具体物質を嗅ぎ分けるテストや、臭いを感じたときの反応を数値化する簡易検査など、嗅覚の程度を評価します。これらの診察・検査結果を総合して、鼻水が透明でネバネバする原因が何なのか診断されます。その上で一人ひとりに合った最適な治療方針が立てられます。
原因に応じた主な治療法
診断がついたら、原因に即した治療を行います。鼻水の原因疾患ごとの代表的な治療法をまとめると次の通りです。
-
アレルギー性鼻炎の治療
アレルギーに対してはまず薬物療法で症状をコントロールします。抗ヒスタミン薬(飲み薬)はくしゃみ・鼻水を抑え、ステロイド点鼻薬は鼻粘膜の炎症と鼻づまりを改善します。抗ロイコトリエン薬や抗Th2サイトカイン薬(生物学的製剤)を用いることもあります。
症状が重い花粉症などでは初期療法として飛散開始前から薬を内服することでピーク時の症状を軽減できます。根本的治療を望む場合、アレルゲン免疫療法が選択肢です。スギ花粉やダニに対する減感作療法として、少量のアレルゲンを繰り返し体内に入れて体質改善を図る方法で、注射による皮下免疫療法か舌下錠を用いる舌下免疫療法があります。数年単位の継続が必要ですが、成功すれば症状が大幅に軽減し薬に頼らず過ごせるようになります。
鼻中隔弯曲症など構造的問題が重なる場合は手術(鼻中隔矯正術や下鼻甲介手術)で鼻通りを改善することもありますが、基本的には内科的治療が主体です。 -
急性副鼻腔炎の治療
かぜから細菌性の副鼻腔炎を発症した場合、抗菌薬(抗生物質)の内服が有効です。典型的にはペニシリン系やセフェム系抗生剤を1~2週間服用します。また、鼻汁を排出しやすくする処置も行います。耳鼻科ではネブライザーによる鼻腔内洗浄・吸引を受けられます。生理食塩水や薬剤のミストを鼻から吸い込むことで副鼻腔の通気・排膿を促し、粘膜についた雑菌も除去できます。 -
慢性副鼻腔炎の治療
慢性副鼻腔炎では、炎症を抑え粘膜機能を改善するために長期的な治療計画が必要です。第一選択はマクロライド系抗菌薬の少量長期投与です。例えばクラリスロマイシン等を通常量の半分ほどで3~6か月服用します。マクロライドには抗菌作用だけでなく抗炎症作用があり、副鼻腔炎の慢性炎症を沈静化させる効果が期待できます。併せてステロイドの点鼻薬を使い、粘膜の腫れを引かせ鼻汁の排出を促します。症状に応じて去痰薬や抗ロイコトリエン薬なども処方されます。
こうした内科的治療で改善しない場合、手術療法を検討します。内視鏡下副鼻腔手術(ESS)では、鼻の穴から内視鏡と器具を入れて副鼻腔の通路を広げ、溜まった膿や増殖した粘膜・鼻茸を取り除きます。手術自体は全身麻酔下で1~2時間程度、入院期間も数日~1週間ほどです。術後は劇的に鼻通りと嗅覚が改善し、粘り鼻水も減ることが多いですが、再発を防ぐため術後も定期的な通院と鼻腔ケアが必要です。 -
好酸球性副鼻腔炎の治療
好酸球性副鼻腔炎は上述の通り難治性です。基本的な治療の流れは慢性副鼻腔炎に準じますが、特筆すべきは副腎皮質ステロイド(飲み薬)の有効性です。ステロイドには強力な抗炎症作用があり、好酸球性副鼻腔炎では術後も定期的に経口ステロイド療法を行うことで鼻茸の再発を抑制します。しかし長期のステロイド内服は副作用リスクがあるため、必要最低限の量と期間にとどめ、併用薬で副作用対策を講じます。
最近登場した生物学的製剤(分子標的薬)は、好酸球性副鼻腔炎に対して画期的な効果を発揮しています。たとえばデュピルマブ(商品名デュピクセント)はIL-4/13受容体を阻害する注射薬で、鼻ポリープや鼻閉の劇的な改善が報告されています。また抗IL-5抗体薬(メポリズマブなど)は喘息と鼻茸の両方に効果があります。これらは重症例に限定されますが、今後治療の主流になる可能性があります。好酸球性副鼻腔炎は指定難病として医療費助成の対象にもなっていますので、専門医療機関で最新の治療を相談するとよいでしょう。
まとめ
透明でネバネバした鼻水は不快なだけでなく、慢性的な炎症のサインでもあります。アレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎は放置すると症状が悪化し生活の質(QOL)が低下してしまいます。一方、適切な治療を受ければ症状は必ず軽減できますし、セルフケア次第で再発も予防できます。
大切なのは、つらい症状を自己判断で放置しないことです。「おかしいな」と思ったら早めに耳鼻咽喉科専門医に相談し、医師と二人三脚で原因に合った対処法を実践していきましょう。専門医の的確な治療とご自身のセルフケアの両輪で、透明でネバネバの鼻水ともきっと上手に付き合えるようになります。快適な毎日のために、今日からできるケアと必要に応じた受診を心がけてください。