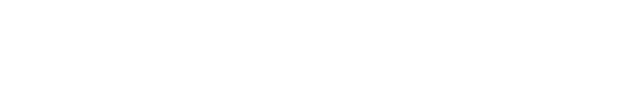咽頭のHPV検査について
増加傾向にある“HPV関連中咽頭がん”を背景に、池袋ながとも耳鼻咽喉科では 咽頭HPV検査 を開始しました。
咽頭 HPV 検査導入の医学的・社会的意義
咽頭がんと HPV:国内外で注目度が急上昇
-
“中咽頭がんの半数超が HPV 関連”
日本の多施設研究では、HPV 陽性中咽頭がん(OPC)の構成比が 31–64 % と報告されており、10 年で右肩上がりに増加しています。pmc.ncbi.nlm.nih.gov -
HPV-16 感染は 15 倍の発がんリスク
米国 NCI の予防 PDQ では、口腔内 HPV-16 持続感染者の中咽頭がんリスクは非感染者の約15倍と示されています。cancer.gov -
若年・非喫煙者にも拡大
従来の「喫煙・大量飲酒」が無い 20〜50 代男性症例が増加。生活様式の変化に伴い、“のど版子宮頸がん” として海外で問題視されています。
“早期発見の壁”とスクリーニング議論
-
症状出現が遅く、発見時に進行例が多い。画像診断では初期病変を捉えにくく、“バイオマーカー検査”への期待が高まっています。
-
しかし、NCI・日本頭頸部癌学会ともに「一般集団スクリーニングの有効性は証明不十分」とし、現時点で推奨はしていません。cancer.gov
-
そのため当院では、学会ガイドラインを順守しつつ「希望者への自費オプション」として提供し、過剰診療にならない運用方針を採っています。
検査技術の進歩――E6/E7 PCR と採取部位最適化
| 技術要素 | 研究での要点 | 当院での位置づけ |
|---|---|---|
| E6/E7 遺伝子 PCR | ハイリスク型 HPV に対し 感度 94–100 %・特異度 100 % の報告。journals.lww.com | 外部専門ラボで同等レベルのキットを使用 |
|
うがい液 vs. 扁桃擦過 |
メタ解析では〈うがい液+口腔スワブ〉平均感度 74 %、扁桃など局所ブラシ 64–75 %。 部位を複数併用すると検出率が 38 %上昇。biomed.papers.upol.cz |
扁桃を綿棒で直接擦過し、腫瘍好発部位にフォーカス。簡便で院内実施可能 |
当院が導入に踏み切った三つの理由
患者ニーズの顕在化
子宮頸部検査・ワクチン普及に伴い、「のども調べたい」という相談が増加。
検査精度が臨床利用レベルに到達
従来より特異度が高まり、「陽性=ほぼハイリスク HPV」 と解釈できる技術的裏付けが整った。
学会の現状を踏まえた“自費オプション”
現時点で学会は集団スクリーニングを推奨していません(後述)。
あくまで本人の意思を尊重し、安全に受けられる場を提供します。
検査概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 18歳以上で「咽頭HPV感染の有無を調べたい」と希望される方 |
| 検体採取 | 綿棒で扁桃表面を軽く擦ります(数秒)。※咽頭反射で「オエッ」と感じる場合があります |
| 検査方法 | 高感度多種HPV検出法(uniplex E6/E7 PCR法) |
| 結果まで | 約2週間 |
| 料金 | 18,000円(税込)〈診察料・検査料・結果説明料込〉 +細胞診追加 3,000円(希望者のみ) |
当院は、現在「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」には対応しておりません。
そのため、当院が発行する領収書は「適格請求書(インボイス)」には該当いたしません。消費税の仕入税額控除を目的とした請求書・領収書の発行をご希望の事業者様におかれましては、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
予約方法
お電話での問い合わせのみ(03-6903-4187)
検査の流れ
-
来院・問診
-
扁桃擦過採取
-
ご帰宅 – 当日の食事制限なし
-
約2週間後:結果説明・医師面談(5〜10分)
検査を考えたい方の例
-
口腔・咽頭がんの家族歴がある
-
複数の性的パートナー歴がある、またはパートナーがHPV陽性
-
喫煙歴・大量飲酒習慣があるが、がん検診を受けたことがない
検査の限界と注意点
咽頭領域で同様の検査体制が確立されていない理由
子宮の領域ではHPV検査は当たり前の検査となっています。そう考えれば、「咽頭でもブラシで細胞を採って調べれば良いのでは?」と思われるかもしれません。しかし、咽頭領域のHPV関連がんについては子宮頸部とは事情が大きく異なり、現在まで有効なスクリーニング手法が確立されていません。その主な理由を技術的・生物学的・疫学的観点から解説します。
前がん病変の不明瞭さ(生物学的要因)
子宮頸がんの場合、HPV感染による異形成が数年〜十数年かけて進行し、子宮頸部上皮内腫瘍(CIN)という段階的な前がん病変を経て浸潤がんになります。このため、細胞診で前がん病変を捉えて治療介入することで癌化を予防できます。
しかし中咽頭がんの場合、明らかな前がん病変(がんの一歩手前の病変)が存在するかどうかすら証明されていません。中咽頭(扁桃や舌根)の組織を経年的に観察することが困難で、HPV感染から腫瘍形成までの自然史が未解明なためです。
実際、現時点では「HPV関連中咽頭がんには子宮頸部のような長い潜在的前がん期がない」と考えられており、細胞診やHPV検査で前がん状態を拾い上げるという発想自体が成立しにくい状況です。この生物学的特性の違いがまず大きな要因です。
検体採取・検査の困難さ(技術的要因)
子宮頸部は膣鏡で直接観察・刷毛で細胞採取が可能な部位ですが、中咽頭(扁桃陰窩や舌の付け根周辺)は視診やアクセス自体が容易ではありません。
扁桃は凹凸や陰窩構造が複雑で、表面をこすって細胞を採取しても、病変部分の細胞が十分取れる保証がないのです。
健常者を対象にした研究でも、うがい液や咽頭粘膜の擦過検体からHPVを検出することは可能なものの、扁桃内に潜むHPV感染を完全に拾い切れない可能性が指摘されています。また、仮にうがい液などの検体から細胞を採取できても、その細胞を顕微鏡で評価して異形を見つけることは子宮頸部より格段に難しいとされています。
疫学的側面・費用対効果
子宮頸がんは若年〜中年女性に比較的頻繁に発生し(検診未実施群では発症リスクが高い)、特定の集団(成人女性)に対し定期検診を行う費用対効果が見込めました。一方、中咽頭がん全体の罹患率は子宮頸がんより低く、特にHPV関連の中咽頭がん患者数は子宮頸がんの約1/10程度と推定されています(高所得国では増加傾向とはいえ、日本でも年間数千人規模)。さらに患者の大多数は中年男性であり、検診対象を男女両方に設定する必要があります。
こうした背景から、大規模な集団スクリーニングを行っても発見できる有意な前がん病変が少なく、コストに見合わない可能性が指摘されます。加えて、口腔・咽頭のHPV感染それ自体は決して珍しくなく、健常人の6〜7%にHPV感染(高リスク型は3〜4%)が検出されるとの調査もあります。大半の口腔内HPV感染は一過性であり、感染者の50%は約1.4年以内にHPVが消失する一方で、7年経っても感染が持続する人が5%程度いるという報告があります。
したがって、仮に全人口に咽頭HPV検査を行えば「HPV陽性」の人は相当数出ますが、その大半は一過性感染で放置しても自然消失するものであり、陽性結果による不安・追跡検査の負担ばかり大きく、実際に将来がんになる人はごくわずかと予想されます。
現に、無症状者に対するHPV検査の陽性的中率(将来のがん発生を真に予測できる割合)は極めて低いと考えられています。このように疫学的に見ても、咽頭がん検診のコスト・ベネフィットは現状では釣り合わないのです。
以上の理由から、HPV関連中咽頭がんでは有効な二次予防(検診)手段が確立できていないのが現状です。専門家も「HPV関連中咽頭がんは二次予防が困難な疾患であり、一次予防(ワクチン)が何より重要」と指摘しています
スクリーニングのエビデンス不足
米国国立がん研究所(NCI)などは「口腔・咽頭がんの一般検診で有効性を示す証拠は不十分」と結論しています。cancer.gov
日本においても、HPV関連中咽頭がんに対する対策型検診(全国民を対象とした定期的ながん検診)は実施されていません。国内の頭頸部がん診療ガイドラインでも、無症状者に対する中咽頭がん検診は推奨されておらず、現時点でエビデンスがない旨が記載されています
表面にウイルスがいないと「陰性」に出ることがあります
HPVウイルスは扁桃の奥深くに潜んでいる場合があり、表面をこすっても見つからないことがあります。そのため、ウイルスに感染していても検出されない可能性(偽陰性)があります。
陽性=がんではありません
HPV陽性と出た場合でも、多くの方は一時的な感染で、自然に体がウイルスを排除します。陽性だからといって、すぐに治療が必要な「がん」というわけではありません。
陰性=安心とは言い切れません
「陰性」と出ても、100%安心とは言えません。先述のように、検査がウイルスを捉えきれないケースもあります。
検査は将来のがん発症を確実に予測するものではありません
この検査はあくまで、今の時点でのHPV感染の有無を調べるものであり、「がんの早期発見」や「発症予測」のための確立された方法ではないという点にご注意ください。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 痛みはありますか?
A. 綿棒で扁桃を軽く擦る程度で、出血や強い痛みはほぼありません。
Q. 検査後にうがいや飲食はできますか?
A. すぐに可能です。特別な制限はありません。
Q. 結果は電話やメールでも教えてもらえますか?
A. 原則ご来院いただき医師が対面で説明します。
Q. 検査は保険適用されますか?
A. されません。自費診療です。